2025年04月03日
ブンとフォー。
2025年 4月2日(水) 雨午後から日差し
北の風 波あり
(ビーチの)シーズン開幕2日目も、連絡船は欠航!
出鼻を挫かれた日帰り業者さんも大変だろうけど、むしろこんな天気で運航されていたら、現地スタッフさんたちはもっと大変だったことだろう。
時系列予報では晴れマークを並べているくせに、完全に雨じゃん、これじゃあ。
連絡船は朝の時点では朝イチの1往復のみ運航という連絡があったのだけど、午後になって海運の公式サイトを見たら「全便欠航」になっていた。
どっちだったんだろう?
なぜ知らないかというと、連絡船の1便が来る前に、我々は自分たちのボートで本島に渡っていたから。
今日もまた、北谷まで南下する用事があるのだ。
幸い雨雲は断続的で、降らない時間帯もあるから洋上で雨に祟られることはなかったものの、南下する道中晴れ間といえば束の間ポッと明るくなるくらいのもので、おおむね雨。
雨の北谷での用事はあっという間に済むもので、なおかつお昼前後になるからどこぞで食事でも。
先日はみはま食堂に立ち寄った。
お味は昔ながらでありつつ、価格は「今ながら」になっていて、いわゆるフツーの食堂も衝撃の価格アップ状態になっていることを知って愕然とした我々。
同じように高騰しているのであれば、もはやフツーの食堂に行っている場合ではない。
というわけで、この日はものすごく久しぶりに金松でステーキでも!
…とやる気を見せてはいたものの、金松もえらいことになっていることを今さらながら知った。
ニューヨークのLサイズは270グラムで2500円、Mサイズだと230グラムで2300円、Sサイズですら200グラムで1700円…。
ちなみに我々が学生時代に、たまの豪華ゼータクディナーで利用していた那覇のジャッキーステーキハウスでは、ニューヨークのLサイズ(250グラム)は当時1050円とか、少々値上がりしても1250円とかだった。
それが今や、ニューヨークのLサイズは2700円になっているらしい…。
この価格でも、今の学生たちは「たまのゼータク」ができるんだろうか。
でもマクドナルドの時給の3倍くらいと思えば、当時とさほど変わらないといえば変わらないか…。
ちなみに貧乏学生の救いの女神的Cランチは、当時350円だったんだけど、現在も550円とかなり健闘してくれているらしい。
ステーキを食べているリッチな友人の傍らで、一人Cランチを食べている学生君もきっといることだろう。
とまぁそんなわけで隔世の感がありまくりの県内ステーキ屋状況ではありつつも、年に一度のことと思えば、ワタシだって清水の舞台から飛び降りるつもりでステーキでも…
…と思っていたのだけれど、実際に北谷に到着してみると、胃袋は特段「肉」を所望していないことに気がついた。
金松であっても否やはなかったオタマサながら、もともと「肉」なヒトではないから、直前の針路変更に文句はない。
というわけで、金松臨時休業というまさかの事態のために用意しておいた次善の策のお店に行くことにした。
こちら。

ベトナム料理レストラン「ベトナムちゃん」。
金松と同じ埋立地ゾーンにあるお店で(反対側に行けば、ダイバーのメッカである宮城海岸、いわゆる「砂辺」になる)、このエリアは相当昔から北谷の他地域に先駆けてポップなお店地帯になったところで、このお店もおそらくこの建物の何代目かのテナントなのだろう。
ちなみにこのエリアは一方通行の道沿いの道に駐車スペースが設けられているんだけど、お店に近いところは満車状態だったから、離れたところに停めざるを得なかった。
おかげで、束の間ながら人生初かもしれないこのエリアの散策ができた。

雨降りだったけど。
浜川漁港を挟んだその対岸には、美浜のアメリカンビレッジが見える(もちろんそちらも埋立地)。

20世紀の沖縄本島しかご存知ない方がご覧になれば、「どこ、ここ?」ってなるだろうなぁ…。
我々にとってはこちら側の埋立地もほとんど「どこ、ここ?」だから完全アウェー状態なのはいうまでもなく、おまけに店内は陸軍の軍服を着たアメリカーだらけ。
料理はベトナム、店員は(多分)ベトナム人、客はアメリカ軍って……いったいここはどこ?
でもベトナムらしいコメの麺を食べたかった我々にとっては、その異国情緒は申し分ない。
井之頭五郎のようにメニューを見ながら熟議に熟議を重ね、まずは前菜として生春巻き@800円を頼んでみた。
ほどなくして、朝ドラ「らんまん」での志尊淳のようなウェイター氏が運んできてくれた。

人生初の生春巻きを食べたその昔、後日自宅で再現したくて本部町内のスーパーで探し回ってもライスペーパーは見当たらず…
…という時代も今は昔、近頃では本部町内のサンエーでさえ、普通に手に入るようになっている。
でも、これは本場モノのライスペーパーなのだろうか、そのようなスーパーで手に入れられるものとは別モノで、中身が透けて見えるほどに透明なくせに、コシは強くて歯応えもっちり、どんなに違いのわからぬ男でもひと口食べるだけでその差が歴然としていることに気がつく逸品。
で、生春巻きにつけるタレといえば、ベトナム料理やさんだけに辛い系なのかなと思ったら、これが大違い。
クラッシュナッツがまぶされているこのタレ、ひと舐めしてみて何かに似ていると思ったものの、なんなのかが思い出せない。
思い出せないまま、具だくさんの生春巻きを完食してから思い至った。
北京ダックのタレに似てるんだ!(※個人の感想です)
もちろんテーブルにはいろいろなドレッシングが並べられていて、辛い系やミョクマム風のものもあったから味変OKになってはいるけれど、この北京ダック風タレでいただくのが最高。
そうこうするうちに、オタマサセレクトのメニューを志尊淳が運んできてくれた。

牛肉フォーMサイズ@1300円。
Lサイズだと1600円になる牛肉フォー、オタマサ的にはSサイズ1100円でちょうどいいところながら、あいにくSサイズはメニューにはなかった。
今ではすっかり日本でもおなじみになっているフォーとはいえ、よく目にするのは鶏肉のフォーで、牛肉フォーとの出会いはおそらく人生初のはず。
オタマサが食べきれなかったぶんをいただいてみたところ、牛肉の出汁が出まくっているスープはレモングラス風味も効いてなんともエキゾチックで、これがまたコメの麺と合うんだわ。

トレーにはフォー用の辛味調味料も添えられていて、試しに入れてみたらこれがたいそう辛い。
それを多少投入して辛味が増してある味は、牛の出汁とあいまってかなりやる気系になっていた。
惜しむらくは、パクチーが最初からトッピングメニューになっていて、デフォルト状態ではパクチー無しという寂しさ。
フツーに入れておいて、特盛りにするなら別途料金にしてくれればいいのになぁ…。
ベトナム料理を食べに来て、パクチー嫌いってのはありえないでしょう?え?あり?
一方ワタシは…

ブンチャーゾー@1300円。
ブンチャーゾーなるものがいったいいかなるものなのか、もちろんのこと知るはずもないワタシながら、食べたことがないってことだけはたしかだったので勇気のチョイス。
でもこれ、どうやって食べるんだろう?
志尊淳が優しく教えてくれた。
トレーにはタレもセットされていて…

…これを丼(?)にダーッとかけて、しかるのちにグチャグチャグチャ…とテッテー的にかき回してからいただくのだそうな。
ちなみにチョンと乗っている筒状のものは揚げ春巻きで、傍らには火を通してあるっぽいクラッシュナッツ、生酢漬けのようなモヤシやニンジン、そして葉野菜類が脇を固めつつ、あくまでも主役はコメの麺。
これがソーメンのように細く、その細いコメの麺のことを「ブン」というんだって。
じゃあチャーゾーって何?
…と思ったら揚げ春巻きのことで、てっきり添え物かと思いきや、実は揚げ春巻きはこの料理の主役の一人だったのだ。
そこにかける甘酸っぱいタレがなんともクセになる味で、冷静になるとなんて事のない味なのかもしれないけれど、なにしろ初体験味覚だけに美味い美味いとモリモリ食べてしまった。
食べ終えてから、グリルチキンのトッピングでもつければよかったかな…と思ったことを付け加えておく。
意外だったのは、このブンちゃんが温かかったこと。
暖かいベトナムのこと、この料理も本来はベトナム版冷麺ってな存在らしく、冷たい状態でいただくものらしいんだけど、そう思って一口食べたら暖かかったので驚いた。
いわばコメの温麺だ。
この日は寒くて雨降りだからなのか、年中そうなのかは知らない。
ベトナムのコメの麺には昔から興味があって、実は現地にはフォーだけではなく様々なコメの麺がある…ということを先年全日空だかの機内誌で知り、この日ようやく、生まれて初めてフォー以外のコメの麺をいただく機会を得たのだった。
ああ、コメの麺を求めてベトナム南から北まで旅したいなぁ…
まぁそれにしても外人客…というか、客がアメリカーばっかりなのには驚いた。
お昼時というのに我々のほかに日本人といえば女性2人連れくらいのもので、軍属間違いなしの家族や2人連れのほか、「US ARMY」のタグ付き迷彩服姿の兵隊さんの多いことと言ったら。
一人で私服のおねーちゃんたち3人と一緒に食事をしている迷彩服アーミーもいて、そのおねーちゃんたちもアジアン風だったから、なんだか陥落する前のサイゴンかどこかみたい…。
そんな客層なものだから、価格ももちろんインバウンド価格になっているのは当然。
いちいちメニューごとに記しておいたとおり、おそらく丸の内のベトナム料理店で食べたほうが安いんじゃないかってくらいの価格設定になっていた。
というか、むしろこの店内では我々がアウトバウンダー?
というわけで、対岸におとぎの国のようなアメリカンビレッジを眺めつつ、ベトナム料理を味わうお店ではアメリカ軍属ばかりという、まことにもって異国情緒あふれるランチタイムとなったのでした。
2025年04月02日
別れの季節。
2025年 4月1日(火) 曇り時々雨
北東の風 時化模様
いよいよ本日から(ビーチの)シーズン開幕!
…のはずが、連絡船はシーズン早々に欠航!
昨日までの予報なら余裕そうだったのに、一夜明けると洋上は遥かに荒れていたのだった。
まさか天気予報がエイプリルフールだったとは…。
それでも雨は前日ほどではなかったので、お昼にはフツーに散歩もできた。
すると…

…ジョビオことジョウビタキのオスの姿が。
ちなみに、ジョウビタキたちとは30年来の付き合いになるというのにこの日初めて知ったところによると、ジョウビタキを漢字で書くと「尉鶲」だそうな。
で、「鶲」はヒタキのことながら、いったい「尉」ってなんのこと?
「尉」とはこの場合、炭火が燃えて白い灰になった状態から転じて白髪もしくは銀髪のことを意味するんだって。
つまりジョウビタキという名前は、オスのこの頭部の色模様に由来しているっぽい。
たしかに初めてオスを目にしたときは、この銀髪カラーがやけに目についたものだった。
この日も我々の歩く先にいて進行方向に逃げるものだから、そのカラーリングはかなり目立っていた。
ただ、こうして背後から見ると黒っぽい鳥に見えるし、尾羽などは濃い色をしていると思っていたのだけれど、飛び去る姿は…

…意外なほどに赤っぽく、最初は別の鳥さんかと思ったほど。
過去にジョビオが飛ぶ姿は何度も目にしてきたのに、真後ろから見たのは初めてかも。
このジョビオが冬の間ずっと島に居たのか、それとも北への旅路の途中にチョロッと島に立ち寄っただけなのかは不明ながら、いずれにせよさすがに4月ともなれば彼ら冬鳥たちは北の国へ帰っていくだろうから、そろそろ見納めだ。
そういえば、今年は久しぶりに内地を訪れたこともあり、オタマサ実家近くでもジョビオ君にも会うことができた。

@入間川
冬の間沖縄にいようと埼玉にいようと、春になると北国へ帰るのは同じで、彼らの夏の住まいは大陸になる。
簡単な説明では「ジョウビタキはシベリアから渡ってくる」と述べられることもあるジョウビタキ、実際の分布域はもっと広く、チベットあたりやバイカル湖周辺、それに中国東北部~沿海州にまで及ぶらしい。
こんな小さな鳥が、そんなところからはるばる渡ってくるなんてなぁ…。
冬は雪だらけでよっぽど暮らしにくいのだろう。
冬の間に日本にやってきているのは、おそらく夏の間中国東北部~沿海州あたりで暮らしているものたちが南下していると思われる。
とはいえ同じ「日本」に来るにしても、埼玉と沖縄じゃ気温も環境も随分異なるだろうに、冬の滞在地セレクトにはどのような判断基準があるんだろう?
遠くまで行くのがイヤなめんどくさがりは埼玉あたりで妥協し、寒がりは沖縄まで南下する…とか?
基本的に繁殖は大陸にいる夏の間に行われ、日本にいる冬場はオスメスそれぞればらばらで過ごしている。
ただし昔から北海道では繁殖が確認されており、近年は初夏から夏の間の日本各地で繁殖が観察されているそうな。
お隣の韓国では留鳥だそうだから、実は韓国くらいの気候が彼らの理想なのかもしれず、そうなると彼らにとって暑すぎるであろう夏の沖縄にジョウビタキがずっと居続けるとは思えないものの、北へ帰るのが面倒になったオスとメスが、そのまま南国でつがいになったりして。
台風で打ちのめされて、「二度と来ないッ!」ってなるかもしんないけど…。
この冬沖縄のどこで暮らしていたのかはわかんないけど、4月に会えたジョビオ君、ではまた来シーズンまでごきげんよう。
2025年04月01日
知られざるベラのタタキ。
2025年 3月31日(月) 雨昼頃だけ曇り
北東の風 けっこう波あり模様
侮れない風が依然吹き続けてはいたものの、前日に比べれば随分おさまってはいたこともあり、本日の連絡船は4日ぶりに通常運航に。
とはいえ雨は、お昼前後の束の間を除いてしつこく降り続く。
異常な少雨のために梅雨前には深刻な水不足に陥りかけていた昨年のこの時期とは、まったく真逆になっている。
これ一事をもってしても、こと気象天候に関しては「平年」という言葉がまったく意味をなさなくなっていることがよくわかる。
ちなみに悪天候続きにもかかわらず、連絡船が欠航していた間もずっと、港の工事は24時間体制で行われていた。
今の日本でここまで工期が切羽詰まっている工事といえば、水納港と夢洲くらいのものだろう。
さてさて、昼前後の束の間だけ雨が上がっていたので、せめてもの運動とばかりに散歩をした。
今の季節はセンダンが花の時期を迎えているから、湿度の高い空気が淀んでいれば、センダンの花の香りが充満していてたいそうかぐわしい。
そのセンダン、いつの間にか島内の随所で育つようになっているのだけれど、以前も紹介したように、島の方々によると昔はこんなに無かったという。
たしかに我々も昔は気にした覚えがない。
成長が早い樹木だから、近年になってドッと増えたのだろうけど、大元はいったいどこなんだろう?
…と朧げながらも疑問に思っていたところ、その答えに最近気がついた。
おそらくこれが、現在の水納島のセンダンバブルの大元だ。

水納小中学校校門そばの花壇に生えているセンダン。
反対側の門柱の傍らにももう1本、そしてすぐ近くにある校長住宅にももう1本育っているセンダンたちが、島内で最も樹齢が長いと思われる。
我々が越してきた頃からすでにここに生えていたのは間違いなく、その頃からヒヨドリをはじめとする鳥たちが実を食べては、せっせと島中にタネを落としまくっていたのだろう。
今の季節、風が吹いていない日に校門にいると、センダンの花の香りがたちこめてます。
実といえば、校門そばのトシおばさんの家で鈴生りになっているのが、こちら。

さくらんぼ。
緑に赤が目にも鮮やかなこのさんくらんぼ、見た目はたいそう美味しそうなんだけど、けっこう渋いので、知らずに食べたらショックは大きいはず。
熟れるともう少し黒ずむんだけど、それでもやっぱり渋い。
その昔は本島までさくらんぼを摘みにいってまでして「さくらんぼ酒」(といっても泡盛に大量のさくらんぼを漬けるだけだけど)を作ったオタマサだったけれど、手間のわりに大して美味しくなかったためにその1回きりで終わってしまった。
寒緋桜のさくらんぼは、味よりもビジュアルを愛でるのが吉。
旧暦では3月3日になるこの日は、沖縄では「浜下りの日」とも言われる。
もともとの意味合いからレジャー方面へと変わってはいるものの、普段海とは縁遠い方も潮が引いた海へと繰り出しては、海神様から食材系をいろいろ賜る「浜下り」、昔に比べてマスコミが取り上げなくなっているような気がする。
それは単に我々が地上波のテレビをほぼ観ないから県内ローカルニュースに接する機会がないためかもしれないけれど、一方で近年の世知辛い世の中では沖縄ですら「漁業権」が幅を利かせるようになっているせいで、レジャーとしての浜下りも実はご法度になっているとか?
ちなみに春から秋までの間は同じ干潮でも昼のほうが潮が引くようになり(秋から冬はその逆)、春の大潮ともなると、まだ最干には間があったこの日の昼時でも、すでにこんなに引いていた。

どこだかおわかりですね?
ちなみに潮が満ちていると…

満ち過ぎていたら砂浜が消えるし、引き過ぎていると砂浜感がなくなる秘密のビーチだから、せっかく歩いてきたのに、満潮時で砂浜が無かった…なんて方もいらっしゃるかもしれない。
そこで遊びたいと思ったら、気象状況はもちろんのこと、その日の時刻ごとの潮の具合いの確認も必要なのが海での遊び。
いつなんどき訪れても希望のモノが用意されているテーマパークに馴らされた方々には無理な世界だからこそ、多くのマリンレジャー業者の経営が成り立っているのだろう。
バナナボートなどのようにただ引っ張ってもらうだけの受動的な遊びに高じている方々の多さに鑑みると、すでに海辺もある意味テーマパークになっているってことなのかも。
そして昔ながらのスタイルで能動的に海で遊ぼうとする方々には、御上からの締め付けがますます厳しくなっていくのだった。
話は変わる。
先日潜っていた時のこと、ふと目をやった砂底で、オトメベラが砂中から何かを引きずり出した。

どうやらクモヒトデっぽい。
咥えただけではクモヒトデは死なないだろうし、かといってすぐさま飲み込めるものでもない。
どうするのかなと観ていたら、オトメベラは…
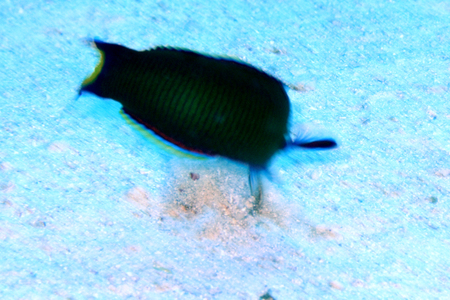
…咥えているクモヒトデを、砂底に叩きつけた!
でも相手が砂じゃ埒が明かないと思ったのか、今度はすぐそばにある根まで来て…

岩肌を使ってしばき倒した!(その瞬間は逃しちゃったけど、砂粒が舞い上がっているでしょ?)
砂が溜まり藻が生えていようとも、砂底よりは効果的と思ったのだろうか。
やがてクモヒトデの「タタキ」が完成したらしく、背を向けてモグモグ食べ終えたオトメベラ。
オトメベラも属しているヤマブキベラの仲間たちではわりと観られる気がするこの獲物の「タタキ」、でもアカデミズムの世界では瞠目シーンらしく、10年以上前のことながらこういう記事がナショナルジオグラフィックに出ていた。
その後ももっぱらベラ類で観られるこのような食事スタイルが、「道具を使う魚」ってことでアカデミズムの世界では注目されているらしい。
そういえば一昨年の春には、ウニの仲間を咥えてどうにもならなくなっているミツバモチノウオに出会ったっけ。

咥えたはいいけれどにっちもさっちもいかなくなっていたらしく、オーバーハング下の暗がりを行ったり来たりしていたミツバモチノウオ、どうするのかなと思ったら、咥えたウニを岩壁に打ちつけ始めた!

トゲトゲに覆われていようとも所詮ウニの殻は脆いため、その一撃二撃で食べやすくなったらしく、その後しばらくするとモグモグし始めたミツバモチノウオだった。
ことほどさように、ベラ類では「道具を使う」ことが一般的なのだ。
それをもってアカデミズムの世界の方々は、魚の知能の高さの表れであるという。
でも同じ「魚」でも、こういう事態に陥っているヒトもいるんですけど…。

過去に何度か紹介している、コクテンフグに手を(口を)出してしまったニジハタの図。
咥えたはいいけれどコクテンフグが膨らんでしまったものだから、これ以上口を開けられず放すことができないニジハタ、そして萎んでしまったら飲み込まれるから、意地でも膨らみ続けるコクテンフグ…。
ひところジョン・ウー監督が多用していた、善玉と悪玉が互いに銃を突きつけ合うシーンのような…

「フェイス・オフ」@ジョン・ウー監督より
…にっちもさっちもいかない状況に陥ってしまっている両者である。
この場で冷静なのは、ジッと見守っているヤライイシモチくらいのものだろうけど、彼はおそらく、その昔デスラー総統がヒス副総統に対してかけたセリフをつぶやいていたことだろう。
「ニジハタ君、君はバカかね?」
これを見せられて「知能が高い」と言われましても…ってところながら、ハタもなにげに賢い魚のグループであることを考えれば、コクテンフグがそれを上回るほど知的だったということなのか。
ニジハタ対コクテンフグはレアシーンだけれど、ヤマブキベラの仲間やモチノウオ類が獲物を何かに叩きつけるシーンは、気にしていれば見掛ける機会はけっこうあるはず。
それをフツーのことだと思ってしまうと「ベラね…」で終わってしまうヒトのほうが多いために、これまでダイビング業界では話題に上らなかったのだろう。
ベラのタタキが実はアカデミズム業界では一部で注目されている…と知れば、ダイバーのベラを見る目も変わってくるかも?
というわけで、当サイトお魚コーナーの「ベラの仲間」が、とうとう100種類に達しました♪
2025年03月31日
ハルミちゃんとミナミちゃん。
2025年 3月30日(日) 雨
北東の風 時化模様
ついこの前まで「4日連続で海に行けるなんて!」と言っていた奇跡の日々は、春休み真っ只中だというのに3日連続で連絡船が欠航という、逆奇跡の日々になってしまった。
しかもこの日などは風こそ昼前後にいったんおさまりはしたものの朝からずーっと雨で、風が再び強まってきた夕刻にボートの様子を観に行った以外は、部屋から一歩も出られない(そりゃ一歩は出たけど…)1日になってしまった。
そんな日には、さすがに歩けば棒に当たる犬にはなれず。
仕方がないから、みかんの食べ比べでもしてみよう。
先日「御見舞い品」としていただいた木原すきすきみかん産の非売品「はるみ」は、なにげに人生初の柑橘類だ。
さてモンダイです、どっちがはるみちゃんでしょう?

はい、正解は左。
右は小玉のいよかんなので、サイズ的にはフツーサイズのいよかんと同じくらいだろうか。
色的にはいよかんとほとんど変わり無さそうに見えるはるみちゃん、しかしながら皮と実の隙間がけっこう空いている分、いよかんに比べて遥かに剝きやすい。
違いは皮の剥きやすさだけではなかった。
その粒を比べてみると…

ひと房の中のツブツブがでっかい。
ツブツブがデカいから食べ応えがあって、その食感はなんだか安政柑とか晩白柚系のような感じだ。
それでいながら酸味はまったくといっていいほど無く、どうやらはるみちゃんは甘味オンリーのツブツブ強調品種らしい。
甘味強調といっても、オレンジやデコポンのように甘味をあとに引きずる系ではないんだけど、甘味のなかにも爽やかな酸味が効いているいよかんが好みの我々にとっては、その酸味の無さはいささか物足りないではある。
とはいえ不思議的爽やかな甘味は、他のどの柑橘でもない味覚だから、はるみちゃんもこれはこれでずいぶん楽しめる。
ザっと調べてみたところでは清見タンゴールとポンカンを掛け合わせて生まれたものだそうで、今のところその生産量は伊予の国がナンバーワンなのだそうな。
ただし生産量自体は極めて僅少なため、全国にあまねく流通しているわけではないらしく、僻地のサンエーでその姿を見かけることはまずないのだろう。
僻地の離島に住まう者にとっては、おそらく産地を訪れなきゃできないであろう味覚体験を、小さな島に居ながらにして楽しむことができたのだった。
ありがとう、すきすき木原。
話はまったく変わる。
雨降りなので部屋でおとなしく最近撮った写真をあらためて見ていたところ、直近のダイビングで珍しくミナミダテハゼを撮っていたことを思い出した。

「珍しく」というのはけっして好みではないからというわけではなく、むしろ共生ハゼたちは昔から興味の対象にしている。
滅多に撮らない理由を強いて挙げるとすれば、たくさんいるから。
砂底の根近くであればどこであれいつも目にするんだけど、「また今度…」と思っているうちに、前回画像記録を残してから1年半以上空いていたのだった。
しかもデジイチになってから撮ったミナミダテハゼの写真を今回振り返ってみれば、なんとなんと、ペアで写っているものが1枚もない!
もともと水納島では個体数が少ないダンダラダテハゼは仕方ないにしても、こと「ダテハゼ」と名のつく他の種類はどれもペアでいる様子を撮っているというのに…。
思い起こしてみても、2匹が同じ巣穴にいる様子は、一度ならず目にしたことがあると思うんだけどなぁ。
そういえばすっかり忘れていたことに、3年前の夏のこと、かなりキバッた色を出していたミナミダテハゼを観ていたら…

…この直後に突如ホバリングした。

似た仲間のヒメダテハゼがホバリングすることは知っていたけれど、ミナミダテハゼも同じようにキバッた動きを見せるとは知らなんだ。
でもこれ、ホントにミナミダテハゼですかね?
水平に近い姿勢のままホバリングするヒメダテハゼとは作法が異なるし、その直前直後の姿はどう見てもミナミダテハゼなんだけど、当時は自信が無かったからペンディングしていたのだった。
まぁしかしホバリングどうこう以前に、まずはペアでいるところをちゃんと撮っておかねば。
水温が温かくなり始めたら、ひとつミナミダテハゼとじっくりお近づきになることにしよう。
続きを読む
2025年03月30日
実は隙間産業。
2025年 3月29日(土) 曇り
北東の風 荒れ模様
本日も引き続き荒れ模様。
もちろん連絡船は早々に全便欠航を告げていた。
そして気温もグンと下がって早春に逆戻り。
それでも激時化ってほどではないし冷え込むってほどでもないから、ガメ公も昼前後にチョロッと外に出てくるほどの気温はあった。
ワタシも機能停止することなく、午前中のうちに昨日の草刈りの続きを終わらせることができた。
畑仕事も一段落していることもあって、そーゆー日のオタマサは、こーゆーものを作ってくれたりする。

今季2度目となる、ローストプチ&中玉トマト。
今季は今月上旬まで不在になりがちだったためか、トマトが甘くない…とお伝えしていたけれど、その後毎日のように主と接するようになって、随分甘くなってきているプチ&中玉トマトたち。
そのうえローストすれば、余計な水分が飛んでさらに甘さ激増。
それもしつこさはなく、酸味が効いた甘さだから爽やかで、ポテトサラダと一緒にレタスで巻いて食べたらたいそう美味しかった…。
さっそく話は変わる。
昨夏オタマサが久しぶりにナカソネカニダマシに遭遇した…と思ったら、実はそれはナカソネカニダマシではなかった、ということがあった。
 撮影:オタマサ
撮影:オタマサと同時に、これまでずっと「ナカソネカニダマシ」として当サイトエビカニ倶楽部内で紹介してきたモノも、実はナカソネカニダマシではないというジジツまで発覚してしまい、慌ててエビカニ倶楽部当該ページを訂正しておいた…
…と思いきや、先日たまたまエビカニ倶楽部のカニダマシたちのところを確認していたら、あらら?当該ページはまったく更新されていないじゃないか。
そこで、朝のうちにやるべきこと(草刈りのこと)を終わらせたこの日、ココロに余裕があるところでひとつ訂正作業を…
…と思ったら、なんてことだ、当方のハードディスク内のファイルは、昨年のうちにちゃんと訂正済みではないか。
ずっとアップし忘れていたらしい…。
慌ててアップ(こちらです)。
カニダマシといえば。
元に戻りつつあるアラビアハタゴイソギンチャクを紹介した先日、実はそこにアカホシカニダマシもいて、面白い動きを見せてくれていた。
このテのカニダマシといえば、普段は大きな鋏脚を↓このようにペタッと下げているポーズがフツーじゃないですか。

イソギンチャクに暮らしている系のカニダマシたちは、その大きな鋏脚は食事の際にも使わないし、ほとんど飾り的意味合いでしかないような感じで、何かに利用している様子を目にしたことがない。
でもごくたまに、この大きな鋏脚をなにやら意味ありげに上げたり下ろしたりすることがあって、両方の鋏脚を掲げたポーズはなかなかに勇ましい。
先日アラビアハタゴイソギンチャクを訪ねた際にも…

まるで周囲にアピールするかのようにその大きな鋏を何度も振り上げては下ろし、振り上げては下ろす動作を何度も繰り返していた。
もっぱら両方を同時に上げ下げするのだけど、時には左右でかわりばんこになることもあって…

…シェーッ!」のようなポーズにも。
そばにもう1匹いたところからすると、これはやはり相手への何かしらのアピールなのだろうか。

でももう1匹がイソギンチャクの裏側に隠れてしまった後も、引き続き同じ動作を繰り返していた。
この鋏脚上げ下げ動作の合間には、お腹を覆っている尾部をペロペロペロ…と高速開閉してもいて、その様子は動画で。
鋏脚の上下とお腹ペロペロ、この動きはいったい何?
アカホシカニダマシたちにとってもイソギンチャクが元気でいてくれないと困るから、ひょっとするとこれは「褐虫藻戻って来い来い踊り」とか?
そうそう、褐虫藻といえば。
またまたイソギンチャク類の白化の度合い話で恐縮ながら、直近のダイビングでも不思議な光景があった。
水深20数メートルで隣り合う2つの根のうち、一方の根のウスカワイソギンチャク(サンゴイソギンチャク)は…

先ほどのアカホシカニダマシが暮らしているアラビアハタゴイソギンチャクと同じように、褐虫藻が戻り始めている。
ところがすぐ隣の根の同じ種類のイソギンチャクはというと…

…相変わらず真っ白のまま。
この根では、ジュズタマイソギンチャクまでもが真っ白になっていた。

ジュズタマイソギンチャクといえば、リーフ際の水深ひとケタくらいの浅いところでフツーに観られるイソギンチャクで、シーズン中はクマノミキッズが集まっていることが多いから、観察する機会は多い。
この日この同じポイントのリーフ際で見られたジュズタマイソギンチャクは、キッズの姿はなかったけれど(白化のために住処を奪われたオトナが来て、キッズを蹴散らしたのかも…)、イソギンチャク自体はまったく元気な状態だった。

ジュズタマはこれくらいの水深(8メートル)にいても今夏の高水温を耐え凌ぐほどのイソギンチャクだというのに、リーフ際が高水温に苛まれている間も絶えず通常の水温もしくはそれ以下だった(28度~29度)昨夏の水深20数メートルで、なぜ白化してしまうのだろう?
ちなみにジュズタマイソギンチャクといえば、その名のとおり触手の節々(?)が数珠の玉のようにポコポコ膨れているのが特徴だ。

一方、白化している方の触手を見てみると…

節(?)はあるけれど、それほど数珠玉になってない。
…って、あれ?
トリミングした上の画像の右端上に写っているのは…

あーっ!!ニセアカホシカクレエビじゃんッ!!
画像を確認してみたら、このイソギンチャクの上にはもう1匹いた…。
白いイソギンチャクの上にニセアカホシカクレエビという千載一遇のフォトジェニックチャンスに、まったく気づいていなかったなんて…(涙)。
涙を呑みつつ本題に戻ると、触手が数珠玉になっていないのは、白化して弱っているために体積が縮んでいるから…と解釈しているんだけど、そもそも種類が違っていたらどうしよう。
というかたとえ種類が違っていようとも、高水温が白化の大きな理由というのなら、それほど水温が上がらなかったから(むしろ例年より低かった)昨夏の水深20メートル以深では、そもそも白化する理由が無かったはずなのに…。
不審死で数年前からどんどん死んでいるのを別にすれば、昨夏の白化でこの水深のサンゴたちにはほぼ被害は無かった。
イソギンチャク類にだけ観られる通常水温での白化現象、しかも白化したサンゴたちのうち生き残れたものには褐虫藻が戻っているにもかかわらず、年間で最も水温が低くなっている今現在でも依然白いままで、なおかつ5メートルと間を置かず隣り合う根同士では、そこに住まうイソギンチャクの褐虫藻の戻り具合いにかなりの差があるこの不思議…。
以前も触れたように、サンゴに比べて褐虫藻が戻るのが遅いことに関しては今回の白化に限ったことではなく、98年の大規模白化でも2016年の中規模白化でも、イソギンチャク類では同じような様相だった。
サンゴの白化について研究しているヒトは多いのだけど、我々シロウトが接することができるこのテの話でイソギンチャク類にだけ見られるこの現象については特に説明はなく、「なるほど、そーゆーことか!」と瞠目するような話には今のところ出会っていない。
ワタシが知らないだけで、実はアカデミズムの世界では、すでに誰もがその理由をご存知なのだろうか。
それくらい当たり前の話なのであれば、いくらなんでもそろそろ世間一般に知らしめてもらってもいいところ。
ところが今に至るもそんな話がなかなか一般にまで漏れ伝わってこないということは、ホントに誰もその理由を知らず、説明できるヒトがいないってことなのか。
疑問をおさらいしてみよう。
高水温下でダメージを与えられた褐虫藻は、むしろサンゴにとっては害になるそうで、そのストレスのためサンゴたちは褐虫藻を排出し、白化してしまう。
やがて水温が下がり、高水温下にさらされなくなると、健全な褐虫藻たちが増えてくるから、サンゴは再び褐虫藻を取り込み、白化していても生きているサンゴは元の色を取り戻す。
ではなぜ高水温下にさらされていないイソギンチャクが白化し、水温が下がってサンゴに褐虫藻が戻っても、白化したイソギンチャクたちにはなかなか褐虫藻が戻ってこないのか。
褐虫藻転バイヤーが価格操作をしているというわけでもないかぎり、水温が下がった海中にはあまねく健全な褐虫藻がいるはず。
にもかかわらずこの両者間での差別、いったいなぜ?
世間的に脚光を浴びるサンゴの研究をするヒトは星の数ほどいても、イソギンチャクは「サンゴと同様…」的な扱いで終わることが多い。
イソギンチャクに特化してその白化のメカニズムの解明を…ってヒトはいないのだろうか。
このイソギンチャクのナゾ、研究テーマ的にはなにげに隙間産業かも。
2025年03月29日
愛しのシモニータ。
2025年 3月28日(金) 曇り
西のち北の風 徐々に荒れ模様
次第次第に北風が強まるという予報どおり、朝のうちはまだ西風でわりと静かだったものが、やがて風はしっかり北に回り、ヒューヒューと音がし始めた。
海況的には午前中ならOKってところではあったけれど、石橋を叩いても渡らない水納海運は、当然のように朝から全便欠航。
おかげで静かな一日に…
…と言いたいところながら、さほどの時化ではないこともあって、今年度の工期が迫っている港の工事は続けられている(でも絶対間に合わない)。
それも、またまた海中の磁気探査か何かをしているのか、ほぼ一日中、陸上スタッフと海中スタッフとで音声のやり取りをしていた。
機器が発達して以降、ひところはテレビ番組でも海中からの実況なんてのがやたらと流行ったものだったけど(今もよくやってんのかな?)、あれって呼吸音と途切れ途切れの話し声が同じボリュームになってしまうものだから、けっこう聞きづらいじゃないですか。
工事現場ではそんな潜っているヒトの話し声がスピーカーから現場用に大音量で出ていて、それが北風に乗って島内に海中実況中継放送をしているようになる。
聞きたくもないのに聞こえてくる聞き取りづらい音声ほど、落ち着かないものはない。
なので午後は音をもって音を制すべく、久しぶりに草刈りをすることにした。
旧チャージ小屋の沿道の草々が春の陽気に誘われてボワッと伸びているので、そのダンパチだ。
そういえば、この冬は一度も草刈りをしなかったなぁ…。
やはり例年よりも寒すぎたから、草々の伸びも低調だったからだろうか。
あ。
今年は1月下旬から3月上旬まで、草刈りどころじゃなかったからだった…。
長期不在にしていた先月、旧チャージ小屋沿道を含めたいろいろなところの草刈りが行われたらしく(おそらく範囲的に見て共同作業だったと思われる…)、一時帰沖した際にはきれいさっぱり刈られたあとだったっけ。
とりあえず沿道の草が道の視界を塞いでしまわないよう、ウリャッ!とばかりに刈り払っておいた。

ホントは左側のサシグサも刈るはずだったのだけど、途中で燃料切れ。
注ぎ足せば続行できるところながら、明日できることは明日やる、それが年を取ってからの健康の秘訣。
というわけで、残りはまた明日。
ところでこの冬の雑草たち、結局伸びはしたものの、それでもやはり寒いと伸び方はかなり制限されているっぽい。
野菜たちもきっとそうなのだろう。でもその分、例年に比べて味がとてつもなく濃厚なことに驚く。
今季のチンゲン菜はビックリするくらいに甘かったし、愛しのシモニータことヒミツの畑の下仁田ネギも…

これはひと月前に撮ったもの
…まるで本土で作っているものかと見紛うほどの中身トロトロの出来栄えで、炒めてよし鍋にしてよし、あまりの旨さに思わずねぎまをリクエストした。
「ねぎま」はもともとネギとマグロの組み合わせだったそうなのだけど、今じゃネギと鶏のモモ肉バージョンのほうが一般的なねぎま。
ただしこれを串に交互に刺して焼こうとすると、シロウトではその焼き加減がなかなかムツカシイ。
ヘタをして材料を無駄にするくらいなら、いっそのこと…

…別々に。
ネギとモモ肉を別々に焼いてから、交互に串に刺し直していただいてみたところ…

…おお、ねぎま!
ビールがビールがススム君♪
愛しのシモニータの旨さもさることながら、今季オタマサ産野菜のなかで最もビックリしたのがこちら。

ザ・セロリ。
これは島の裏あたいのものなんだけど、ヒミツの畑の日当たりの良いところに少量植えられているものは、これが同じセロリかと見紛うほどに遥かに巨大で(2倍以上)、なおかつ色濃く、それでいて固すぎず育っていて、先日オタマサが収穫して炒めたものを食べてみたら…

メチャクチャ美味しいッ!
セロリで濃厚な甘さを感じるだなんて、人生初かもしれない…。
その昔まだ紅顔の美少年だった頃、テレビCMの名高達郎に騙され、生セロリをヨーグルトにつけて食べて以来セロリ嫌いになったワタシは、セロリを美味しくいただけるようになるまでに、それから四半世紀の時を費やしてしまった。
10代20代の頃はKFCのコールスローサラダも食べられなかったほどだったことを思えば、この濃厚かつ甘いセロリが人生最初の出会いだったら、その後の人生は大きく変わっていたろうなぁ…。
寒さが味に与える影響は、野菜だけではないらしい。
3月になって春っぽい陽気の日が続くようになった頃、リュウキュウアサギマダラたちも俄然やる気モードになってきて、庭のツルモウリンカに引きも切らずやってくるようになった。
しばらくすると、そこかしこの葉の裏側に卵が産みつけられていて、やがてそれらが孵化しはじめた。
暖かいわ数は多いわで、パッとほんの一角を見ただけでも…

奥にいる激ピンボケのものも含めれば、この視野だけで6匹ものイモムシ君の姿が。
これがここのツルモウリンカ全体となると相当なイモムシの数で、この時はまだ2齢幼虫くらいのサイズのものが中心だったからまだしも、それからほんの2週間弱で、ツルモウリンカはこうなってしまっている。

葉っぱ食われ放題。
大量にいる終齢幼虫サイズがムシャムシャ食べ漁っているんだもの…

…そりゃ葉も無くなろうってもの。
そのとばっちりを受けているのが、ひと足先にサナギになっている先輩さんたちで、雨を凌げるようにちゃんとツルモウリンカの葉の裏でサナギになっていたはずなのに、その葉が食べられてしまったものだから…

…葉は葉脈だけになってしまって雨ざらし。
ひと足早く孵化し、葉がたっぷりある間に栄養を摂ってサナギになれたまでは良かったけれど、後輩たちのまさかの攻撃にさらされている先輩たちなのだった。
こんなに卵を産みに来るってことは、やはり他よりも美味しく見えるのだろうか、このツルモウリンカ。
それにしても、いくら美味しそうに見えるからといってもこれだけ誰も彼もが卵を産んだら、やがてこの先幼虫たちのエサが無くなるなんてことはわかりそうなものなのに、本能はそこまで理解が及ばないのか。
あ。
どこかで静かに地球を観ている宇宙人も、地球人類に対して同じ思いを抱いているのかもしれない…。
2025年03月28日
新登場は初登場。
2025年 3月27日(木) 曇り時々晴れ
南のち南西の風 波あり
連絡船の船長によると、今日までは通常運航で、翌日以降はヤバそう…という話だった。
モンダイは、その「以降」がどこまで続くか。
この塩梅だと、なんとなく今月は本日これにて終了ってな気配もある。
となると、来月1日からのシーズン開幕(当店ではなくてビーチの営業の話)に向けて準備しておかなければならない身としては、事前に手配できるのは本日がラストチャンスになる。
というわけで、午前中に本島まで連絡船でお出掛けし、午後イチ便で帰還。
どうせ本島に出るのなら、最終便までゆっくり滞在していたいところではあったんだけど、この日のうちにやっておきたかったことが少々あったのだった。
そのひとつがこちら。

ごくごく一部の間で名作との誉れも高い、「ウミシダス」Tシャツのニューカラー登場!(画像にリンクはってあります)
在庫切れのものを同じ色で追加するよりも、この際違うカラーで…ということで、夏に向けてにぎやかなオレンジに。
細々ながらも少しずつ売れていくうちに品切れになっていくTシャツたち、だからといって冬の間の需要は僅少なので、どうしても追加発注は春先になる。
でまた発注しなければならない種類が多く、おまけに印刷をお願いしている業者さんにオーダーできる最小ロットが1種類につき10枚からなので(昔は5枚からOKだった…)、在庫切れのものを全部追加したらそれだけで破産してしまう。
なので第一弾として選ばれしものたちを追加したついでに、このオレンジの登場となった次第。
一方、毎年この時期に登場させている新作、この程度の絵柄など、チョチョイノチョイといつでも描けるだろうと思われているかもしれないけれど(そういう場合もあるけど)、出来の良し悪しはともかく、昔ながらのアナログ手法のために、絵柄を決めるまでにはけっこう時間がかかるもの。
今年はその大事な時期にそれどころじゃないことになっていたので、新作Tシャツのデザイン検討にかけるべき時間が無い…
…はずのところ、「チャンスは最大限に活かす、それが私の主義だ」とその昔赤彗星に教わったワタシは、上京中に何度も利用した電車の中をその「チャンス」にしたのだった。
乗車中、うつむいてスマホを見てばかりいる多くの方々のその背中の荷物に、そして上着に、やたらと目についたのが、とある有名ブランドのロゴマーク。
それが有名ブランドであることは知っていたけれど、あくまでもアウトドアウェア方面でのことだとばかり思っていたから、バッグであれ上着であれ、カジュアル利用のアパレルアイテムになっているなどとは知らず、その利用者が多いことに驚いた。
一両の車内に10人くらいはいたものなぁ…。
連日の通勤や待機日に電車に乗っている際、ずっとそのロゴマークを見ているうちに、神の啓示が舞い降りた。
そうだ、これを今年のTシャツに…。
さっそく2月の一時帰沖中にデザインを決定し、今月になって一時帰沖のはずがずっと居られることが確定してから、ようやく発注。
そしてこのたび、ついに完成いたしました、今年の新Tシャツ!

その名も「ホースフェイス」(画像にリンクはってあります)。
もちろんモデルは、スーパー馬面フィッシュのヘラヤガラだ。

世の中にTシャツ多しといえども、ヘラヤガラをモデルにしているTシャツなど、そうそうないはず…。
ただ、当初神の啓示を受けた際には頭の「N」を「H」に替えりゃいいだけじゃん!と、自らの思いつきを自画自賛していたのだけれど、よくよく考えたら(考えなくても)末尾は「TH」じゃなくて「SE」だったから焦った…。
でもそのおかげで「E」が縦に3つ並ぶという、測ったようなデザイン性の高さ(?)が生まれたのだった。
それはそうと、「ウミシダス」の新色のせいでパロディものがかぶってしまったけれど、いつもいつもこの路線ってわけじゃないですから、当店のTシャツの存在を初めてお知りになった方々におかれましてはどうか誤解なきよう…。
ちなみに今回の新作は当店初となるドライTシャツなので、従来の綿100パーセントの生地とは異なります。
ドライTシャツはポリエステル100パーセントの素材で、吸水性と速乾性に優れる特徴を持つほか(綿の2倍を超える速乾性)、UVカットの能力も高く、軽い着心地、見た目も手触りも爽やか、高い通気性などなど、ジョギング等日々の運動のお供としても最適。
また、高い伸縮性があり、洗濯を繰り返しても型崩れも色褪せもしにくいので、長くご利用いただけるスグレモノです…
…といいことづくめなんだけれど、それでもやっぱり綿100パーセントが好き♪って方も多いだろうから、今さらながらの当店初登場ドライTシャツ、従来商品とは生地が異なるということだけはご留意くださいませ。
2025年03月27日
天使と悪魔。
2025年 3月26日(水) 朝晴れのち曇り
南の風 やや波あり 水温21度
一夜明けて目覚めたら、筋肉痛で体がガタガタ…
…になっているかと覚悟していたのに、意外なことに多少の疲労感はあってもどこもおかしくない。
やはりこれはオタマサ実家での自主トレ(?)のおかげだろうか。
それとも、単に高齢化で痛覚が劣化しているだけなのだろうか…。
ともかくなんともないので、翌日以降の雨の連打の前の最後のチャンスであるこの日を無駄にせずに済んだ。
というわけで、朝から海へGO!
…と書くと、なんだか山へ海へ遊んでばっかりなように思われるかもしれないから慌てて書いておくと、長らく品切れ状態が続いていたTシャツの再入荷をお伝えするなど、いろいろとシゴトもしてるんですからね。
新作Tシャツも近日発売開始予定なので、乞うご期待!
…さてさて、朝方はけっこう晴れていたんだけど、このあとだんだん下り坂になる予報のとおり、だんだん分厚い雲が空の縁辺に見え始めてきて、時々雨もパラつきはじめた。
それでも全体的にはおおむね晴れ間も見えたりする曇り空で、まぁ完全無欠とは言わないまでも、南風で暖かいからまずまずの海日和。
そして海中は、工事現場から離れたところにしたのがよかったのか、ここのところでは最も快適な透明度で、久しぶりに海中にいるコト自体が心地よかった。
そんな春めいた気分が功を奏したのか、オタマサとは違ってこのところウミウシといえばコイボウミウシ系しか目につかなかったワタシのウミウシ節穴目でも、ポコポコポコ…とお馴染みのウミウシさんたちの姿を見かけることができた。

特に探しているわけでもないのに目に入ってくるのだから、本気で探せばきっともっとたくさん…
…と言いたいところながら、その「本気で探す」という行為そのものがクラシカルアイにはそもそも苦行なのだから、ウミウシといえばこのように勝手に目に入ってくるものとしか出会えないワタシ。
一方オタマサは、クラシカルアイ度ではあっという間にワタシを追い越しているにもかかわらず、何度も言うように30度の視野に限ってはヒト3倍の集中力を発揮できるものだから、今日もまたこういうものを教えてくれた。

さてモンダイです、↑この画像のどこに何がいるでしょう?
画面小さめのスマホでご覧になっていればおそらくそれが実物大だから、画像をピピッと拡大して見ないように。
浮遊物がたくさんついてしまってみすぼらしくなっているガヤの一点をオタマサが指さしてくれるものの、ワタシには何かが動いている…くらいしかわからず。
いっそのことすでに撮っているであろう写真を見せてくれと頼んだところ、再生ボタンをポチッと押したカメラの液晶画面を見せてくれた。
その画像を見て、「おお、ハタタテギンポの1種の激チビターレか!」と喜び、ちゃんと正体がわかるように撮ってみたらば…

…それはウミウシなのだった(↑この画像は天地を逆にしてあります)。
1センチほどのものをこんなに大きく撮れるクローズアップ装備ではないので、この画像はもちろんトリミングしてあるのだけど、画面の外にはこういうものも写っていた。

グルグル巻いている黄色いもの、これはやはりこのウミウシの卵なんですかね?
で、このウミウシさんはいったい誰?
図鑑を見ていてもすぐに匙を投げるオタマサにかわり、グーグル先生に尋ねてみたところ、これはどうやら「ホソミノウミウシ」もしくは「ミズタマカヤウミウシ」という、まだ和名だけあって学名が記載されていないウミウシっぽい。
根の片隅にポツンと生えているショボショボのボロボロに見えるガヤをサーチしては、このような小さなウミウシを見つけることは得意でも、それがいったい誰なのかという話になると、たちまち集中力が2歳児級になるオタマサである。
ウミウシは多種多様でコレクションアイテムにもなるから、今さら言うまでもなくダイバーに大人気のクリーチャーとなって久しい。
でも同じ軟体動物でも、各種ウミウシと比べると天使と悪魔ほどの違いがあるものもいる。
まったく歓迎されないどころかむしろ害虫ならぬ害貝認定されている軟体動物が、ご存知シロレイシガイダマシだ。
昨夏のサンゴ白化後、エサを求める彼らが生き残っているサンゴに寄り集まっている…という話はすでに何度も紹介しているとおり。
ただ、年明け後に潜ったポイントのリーフ際では、シロレイシガイダマシの食害痕は見えても貝自体は妙に少なくなっていたので、シロレイシガイダマシバブルもついに終焉を迎えたのかな?と一瞬勘違いしてしまった。
その後違う場所で潜ってみたところ、やはり以前同様にシロレイシガイダマシだらけだ。
はてさて、この密度の違いはいったいどういうことだろう?
ひょっとして…。
…という疑問は、先だってのビーチ清掃作業時に明らかになった。
顔見知りの本島の業者さんと話していた際に伺ったところによると、シロレイシガイダマシ大量発生を受けて、本部町ダイビング協会としても、個々に排除活動をしているのだそうだ。
もっぱら安全停止の時間帯にできる範囲で…とか、ゲストを案内する係ではない船長が…などという具合いに個々の作業ではあるらしいとはいえ、みなさんがそうやってシロレイシガイダマシの大量発生を問題視してくださっていることに勇気づけられたワタシである。
というか、本島から潜りに来ている業者さんのなかには、
「シロレイシガイダマシ?それなんですかぁ?」
なんていうガイドもいるんじゃないか…と疑っていたワタシをお許しください…。
そのシロレイシガイダマシ、みなさんの排除活動が及んでいないところでは、相変わらず…


…ウジャウジャ。
BCのポッケに入る程度の排除をしたところで所詮焼け石に水でしかないかもしれないけれど、枝間に入り込んでいるものならいざしらず、このようにテーブルの上で集合しているものは根こそぎ排除できるから、ともかくすべてBCのポッケに入れてしまう。
これだけでもうポッケはパンパンだ。
依然としてサンゴを食べまくっているシロレイシガイダマシたち、本格的に排除作業をするとなれば、洗濯ネットを3つくらいと長めのピンセットを持って入んないと「成果」は出そうにない…。
2025年03月26日
石川岳登頂作戦。
2025年 3月25日(火) 晴れ
南西の風 おだやかのち波あり
秘密基地にて一夜を過ごした翌朝、我々は朝7時30分には大浜のお弁当屋さん「でいご」に到着していた。
ここでお弁当を買って、今日も南下するのだ。
ハフトゥミッションのための南下だった前日とは違い、この日はいわば娯楽のため。
それなら2日続けて南下するのではなく、日を改めて…ってことにしたほうが、時間的にも肉体的にも余裕を持てるところではある。
しかしながら、あいにく週間天気予報ではこのあと雨の連打になる見込みとなれば、少なくとも今月中は今をおいてほかにチャンスはない。
来月になったらなったで、一寸先は闇の我々に来月がある保証もない。
というわけで、この日に決行とあいなった。
その「娯楽」とはなにかといえば、ほかでもない、オタマサのバースデー登山である。
昨年の本部富士登頂同様、お金がかからないプレゼントとして選ばれたワタシの肉体奉仕、今年はいろいろあったために、ホワイトデー登山と一緒くたになってしまった(そもそも2月にチョコをもらえる状況ではなかったからホワイトデーは関係ないんだけど)。
今回目指す頂は、うるま市にある石川岳。
その昔登った山に再び…という案もあったものの、いまだ知らぬ山もまだまだたくさんあるから、せっかくなら初めてのところへ…ということになった次第。
もっとも、石川岳といえば標高はたかだか204メートル、しかも石川青少年の家が管理運営している登山コースで、ファミリーでも気軽に楽しめる山…
…というイメージだったから、すでに本島内の名峰(?)をいくつも登っている我々としては、完全にタカをくくっていた。
ところが…。
下の道を通って石川青少年の家の駐車場に着いたのは、ちょうど施設のゲートがオープンする8時30分。
駐車場には他に車は無く、施設内にある登山道入り口からの入山者としては、どうやらこの日の一番乗りらしい(施設外にある別の登山口利用という手もある)。
石川青少年の家はこんなところにあるものとしてはビックリたまげるほどに立派な施設で、それもこれもキャンプコートニーやホワイトビーチをはじめとする、米軍施設を有するがためにもたらされる基地マネーの賜物なのだろう(※個人の勝手な推測です)。
施設内の登山口を利用する登山者は、事務所で受付をしておく必要がある。

オープン早々にもかかわらずすでに事務所内は職員がみなスタンバっていて、窓口ですぐさま対応してもらえた。
代表者の名前や入山時刻、選択したコースなど各記入事項を用紙に書いた後、初石川岳の我々には可愛らしいおねーさんが親切丁寧に教えてくれた。
石川岳にはA、B、Cとコースが3つあり、アルファベットが下るにつれて、所用時間や距離、難度が上がっていく。

事務所で受付するともらえる地図
ただ頂上を目指すだけならAコースで充分ながら、我々の興味の対象としては、渓流沿いに歩けるというCコースが最も魅力的だ。
それにしても、フルマラソンならいざしらず、いかに個人差があるとはいえ3時間~5時間という2時間もの誤差想定はいかなる理由によるものなのだろう?
何かを見つけて立ち止まる時間が人一倍多い我々の場合、このように想定されている時間の1.5倍かかることが常だから、5時間の1.5倍となるとこの日のうちに島に戻れなくなっちゃうかも…。
ともかくCコースで行くことにし、事務所から歩いて10分ほどのところにある登山道入り口に向けて施設内を歩いていると、目指す頂上らしき頂が見えてきた。

やがて登山道入り口に到着(その手前に最終トイレがある)。

ただし「登山道入口」といいつつ、道は最初から下り坂に。

それもけっこう急勾配で、ロープに頼らなきゃならないくらい。
これから登ろうというのに、何もいきなり下らなくても…
…と思っていたら、道はにわかに急な上り坂となった。

登山口に入るまでは、ふと振り返ればうるま市の喧噪がすぐそばに感じられる景色だったのに…

早くも世界が亜熱帯のジャングル地帯になっているこの不思議…。
急な登り道はさらに続き、ロープがなければ辛い場所も。

この先もまだまだ急な上り坂で、普段ジョギングをしているオタマサはともかく、普段の運動といえばウォーキングがせいぜいのワタシなど、早くも動悸・息切れが…
…となるこの道のりを、管理事務所はこのように名付けていた。

ナットクでやんす。
ワタシの場合は、下手をすると「心停止の坂」になるかもしんないけど。
この急坂が終わると、やがて常識的な勾配の道のりになった。
その沿道に、なぜだかそこにだけ咲く大輪の花々が。

ケラマツツジですかね?
園芸品種になっているからさして珍しい花ではないものの、このように野辺に咲いているのを観るのは初めてかも。
でもこれって、ホントに天然なのだろうか?
沿道に人の手で植えられているとかってことは……。
やがて道は、AコースとB、Cコースの分岐点に。

すなわち、当初はCコースで行こうと思っていたけど、しんどいから短縮コースにします…って手もあるわけだ。
もちろん我々は、当初の予定どおり、右の道を行く。
分岐点からしばらくは、細い木立に囲まれた平坦な小径が続いた。

暑くもなく寒くもなく厳しくもない平坦なこの道で息を整えているうちに、やがてルートは「道なき道」のような亜熱帯世界になってきた。

見上げる頭上は、木々に覆い尽くされている。

図上がこんなふうだから日差しといえば木漏れ日程度で、しかも細流が流れていることもあって湿度も適度。
いやはや、なんとも過ごしやすい。
そういう環境は、こういう植物にも最適らしい。

遥かなるイスカンダル…じゃなかった、イルカンダの花。
けっこう太くなる蔓性植物の花で、その蔓に沿ってこの花が連なっている様子があちこちで見られた。

以前もどこかで見た覚えがあるのだけど、どこでのことだったか思い出せない…。
やがてBコースとCコースの分岐点があり、その先にちょっとした広場があったので小休止することにした。
この広場は以前まではアスレチック的遊具があったようなのだけど、現在はただの広場になっている。
遊具でケガした子がいたからか、老朽化著しいためなのか、撤去の理由は不明ながら、遊具が無くなっているため「ターザン広場」という名称がまったく意味不明になっていたりする…。
さてさて、その先はいよいよCコース。
序盤は渓流沿いなのだけど、ほとんど沢下りといっていい道のりで、ロープを伝って岩を降りるところまであった。

その後しばらくの間は、もっぱら沢を歩くことになる。

事前に調べていたからこれがコースであることはわかるのだけど、知らずに来たら、これであっているのかどうか、かなり不安になるかも。
でもこれがコースであることを示す矢印がところどころにあるあたり、ちゃんと管理が行き届いている。
一見すると長靴かダイビング用のブーツでもなければずぶ濡れになってしまいそうながら、石伝いに歩けば靴の中まで濡れずに済むようになっていた。
ひょっとしてこの石も、濡れずに歩けるようにわざと置いてあるんだろうか?
とはいえそれなりに険しいところもあったりはする。

このあたりから水音が大きくなってきた…と思ったら、このゾーンを過ぎたところが…

…ささやかな滝になっていた。
ルートは写真右側の岩を降りてくるようになっているから、視野30度しかないオタマサなどこの滝に気づかずそのまま通り過ぎようとしたほどのこの小さな滝にも名称がついていて、静かに眺めてみれば、涼感たっぷりのいい水辺だ(こういうところには名称ボードは無いほうが…)。
このすぐ先から、ルートはようやく渓流と別れて再び登り道になるのだけれど、その登り道に入るその先に、細流の淀みがあった。

魚でもおりはせぬかと眺めるオタマサ、しかし魚影はまったく見えず。
そのかわり、ここに至るまでにもやたらと目にしたとある生き物が、この淀み(「友愛の池」なる名称アリ)にはめちゃくちゃたくさんいた。
とある生き物とは…こちら。

(おそらく)タイワンオオミズスマシ。
オオというだけあって、知らなければミズスマシだとはとても信じられない1センチ超サイズで、細流のちょっとした淀み部分でチラホラ姿を見かけた。
子供の頃からその存在は知っていたミズスマシながら、水田だらけだった環境にもかかわらず子供の頃にその姿を目にした覚えはまったくない。
そんな昆虫少年的にはレアなミズスマシが、特大サイズとなって現れてくれたからには、思わず動画で撮ろうという気にもなるもの。
オオミズスマシ、なんだか心地よさそう…。
肉眼ではその姿を捉えきれないものの、図鑑の写真を見てみると、前脚が最も長くなっていたのが意外だった。
彼らはゲンゴロウのように後ろ脚で泳ぐわけではないのだ。
そうそう、昆虫といえば、もう1種初遭遇がいたんだった。
こちら。

沢伝いに歩いているときに突然ここに舞い降りてきた1センチほどの虫で、メタリックなボディを目にした瞬間はまたぞろキンカメムシ系のカメムシかと思った。
でもよく観ると、コメツキムシとかタマムシにそっくりな姿形をしている。
帰宅後調べてみたところ、これはどうやらミドリナカボソタマムシという南方系の種類らしい。
この方面の変態社会において激レア扱いされているものではないとはいえ、サイズ的に探して見つかるものでもなさそうだから、なんだか得した気分。
一寸に満たない五分のムシにも喜べる魂。
さてさて、いよいよ細流をあとにして登り道に突入。

いきなりロープウェイ…。
その先も、ロープを必要とはしないまでも、けっこう急な勾配の登り坂が続く。

ヒーヒーハーハー登っていると、多くの皆さんが同様になるのだろう、人呼んでこの道のりは…

再びナットクでやんす…。
そんな無言の坂を登っているうちに、ようやく尾根道になった。

地形がこうなれば、頂上はきっとすぐそこだ。
…と安心させておきながら、途中下り坂もあったりして再び登らされたりしつつ、ついに…

…到着!
山頂には写真のような見晴台があって、204メートルよりは少々高い位置に立つことができるようになっていた。
その見晴台からの眺め。

でいごで買ってきたお弁当をこの山頂でいただき、人心地ついてから下山することにした。
Cコースはいわば遠回りをして山頂を目指すコースだからここまで時間がかかったけれど、下山コースどおりに降りるとなれば、途中「しりもち坂」なる急な下り坂から始まる急勾配がつづくものの、急勾配な分あっという間に登山道入り口、すなわちスタート地点に戻ってきたのだった。
トータルで3時間ちょい。
オタマサはともかく、ワタシが途中くじけることなく踏破できたのは、ひとえにオタマサ実家で散歩尽くしの日々を送っていたおかげ。
待機を余儀なくされていた日々が、思わぬ自主トレになっていたのだった。
それにしても、これほどゆっくり行っても3時間なのに、5時間かかることもあるってのはどういうこと?
…と思ったら、それはおそらく「城の展望台」までの寄り道コースも回った場合なのだろう。
というわけで無事下山し、再び事務所にて下山時刻を記入して、石川青少年の家を後にした。
到着した朝にはピースケ号しか無かった駐車場には、30台ほどの車が停まっていた。
山頂やコースでは我々のほかにも人が行き来していたから、平日でも日中はそれなりに人が来ていることはわかっていたけれど、停まっている車にはレンタカーが1台もなし!(Yナンバーはあったけど)
すなわち、インバウンダーゼロ!
なんだか気分爽快。
目標を達成し、心地よい運動で身も心も充実したところで、自らにご褒美だ。

久しぶりにクリームクリームで「ぜんざいクリーム」(のミニ)♪
ちなみにこれはバースデー登山の延長だから、ここはひとつワタシがおごりましょうということになっていた。
であれば、この際とばかりに普段食べないスペシャルなものを選べばいいものなのに、お昼にお弁当をしっかり食べて別腹もないオタマサが食べられるものといえば…

ソフトクリームのお試しカップサイズ@200円なのだった。
なんとも安上りな女なのである。
ところで、今回久しぶりに訪ねて驚いたことに、クリームクリームさんには5台分の駐車スペースが設けられていた。
路駐が多いから、おそらくご近所さんにいろいろ言われてのことなのだろう。
でも…。
この午後は引きも切らずお客さんが訪れていたにもかかわらず、我々以外の誰一人として駐車スペースを使っていなかったのだった。
たいして交通量があるわけでもない路上のこと、パッと停めてチャッと買ったほうが楽ちんではあるわなぁ…。
そんな駐車スペースが価格に反映されているわけではないだろうけれど、コロナ禍前は100円だったお試しサイズがある時から150円になり、今ではその倍になっているのだから(量もちょっと増えているけど)、我々がこのように気軽に立ち寄れるのも、この先そうはないかもしれない…。
それを考えると、受付するだけで駐車場も入山もすべて無料で済む登山のなんと素晴らしいことか。
こういうところで楽しめない方は、せいぜいジャングリアで亜熱帯気分に浸ってください。
2025年03月25日
幻の黒。
2025年 3月24日(月) 晴れ
南西の風 おだやかのち波あり
午後も遅くなってからやや波が出てきたものの、今日もおおむね海日和。
となると、これで5日連続で海へ!
…と行きたいところながら、暮らしの中には何かとハフトゥミッションがある。
本日は北谷まで行かねばならない所用があるのだ。
ボートで本島まで行く予定だったから、連絡船の運航時刻に縛られることはない…
…はずだったのだけど、本日は郵便物が届く予定になっていた。
それもナマモノなので、留守中に放置プレイというわけにもいかない。
そのため渡久地港で郵便配達レディから荷物を受け取る必要があったので、9時前には渡久地港に到着して、無事荷物を受け取った。
その荷物というのもまた不思議で、そもそも同一宛先に3個口で発送されているのに、なぜだかそのうちの2個だけ先週届いていて、残りの1個だけこの日の配達になってしまったのだ。
もちろん本部郵便局もあずかり知らないところで、先週は首をひねりながらの配達となっていたのだった。
届いた荷物にはちゃんと1/3、2/3、3/3とそれぞれ同一宛先への3個口の荷物であることを示すシールが貼られているというのに、いったいどういうこと?
ちなみに先に届いた荷物というのは木原すきすきみかん産いよかんで、我々が3月上旬まで島にいたり上京したりを繰り返していたから、発送するタイミングを計ってくれていたもの。
そのいよかんたちはちゃんと注文して購入したものなんだけど、この日届いたものはすきすき木原氏が「お見舞い」として贈ってくれた柑橘セット。
それらは3個口の荷物として今治から発送されたはずなのに、どうして「お見舞い」の品だけ遅れてしまったのだろう?
ひょっとして、箱のサイズがそれひとつだけ異なっていたから?
だったら「1/3」などのシールの意味はどこにあるんだ…。
空港で飛行機に載せる段階で、2個載せたら満杯となり、1個はあとまわしになっちゃったとか?
ともかくそんなわけで、出先で受け取ったものだから、秘密基地の冷蔵庫は大変なことになっている。

晩白柚に次ぐジャンボサイズの安政柑が、一段まるまる占拠。
さらにレモン、ネーブル、はるみちゃんといったそうそうたる顔ぶれに満たされ、冷蔵庫はうれしい悲鳴をあげているのだった。
ところで、本来ならこちらからお見舞いをしなければならないかもしれない今治、木原すきすきみかんは大丈夫なのだろうか。
お礼かたがた電話で尋ねてみたところ、騒ぎになっているところは今治市のまったく正反対の場所だから、彼らに被害はないらしい。
それにしても各地で相次ぐ山火事騒ぎ、とうとう日本もカリフォルニア州のようになってしまったのか…。
さてさて、北谷での用を済ませたら時刻は昼過ぎで、どこかこのあたりでランチを摂らねば。
このところはどこかに行くと普段は食べられないもの系のお店にばかり行っていたから、久しぶりにフツーの食堂に行きたくなった。
探せばいろいろあるんだろうけど、このあたりで我々が知っている「フツーの食堂」といえば、こちらのお店。

ご存知みはま食堂。
昨年同時期に寄った際にはまさかの臨時休業で涙を吞んだものだったけれど、この日はフツーに営業してくれていた。
初めて寄らせてもらった8年前と比べればかなり色褪せた看板、それがむしろ地元に愛されている度を示しているようにさえ見えて貫禄たっぷり。
そのとおりお客さんはほぼ地元客で、インバウンダーや国内旅行者で溢れかえるアメリカンビレッジあたりの各お店とは、完全なる別世界…というか、そもそもあるべき姿でなんとも落ち着く。
ただし田舎から出てきた我々が落ち着かないのが、都会の食堂プライス事情。
オタマサが頼んだ「みはまそば」は…

…このフツー盛りでなんと900円!
ワタシがチョイスしたスパイシー牛肉もやしそばともなると…

…もともと各そば屋さんでも高級メニューだったとはいえ、これで1100円!
入り口近くにある食券機に並ぶメニューを見たかぎりでは、ズラリと並ぶ食事メニューのうち、1000円未満でいただけるものといったらオタマサが頼んだみはまそばと中味そば、そしてザ・そばの3つしかない。
ちなみに8年前に訪れた際には850円だったそばセットは、今では1400円にパワーアップしていた…。
オタマサも、あまりの価格上昇に放心状態である。

(前日の清掃作業で素人焼けしているともいう)
それでもお味は相変わらず抜群で、牛肉もやし系の変化球メニューは元祖前田食堂をはじめ、今ではどこでも目にするようになっているけれど、こちらのスパイシー牛肉もやしそばは、ワタシ史上ナンバーワンのお味であったことは特筆しておかねば。
ちなみに、我々と同じタイミングで食券機に並んでいた地元のにぃにぃたちは、1500円もするみはまそばセットをフツーにポチッとしていた。
それだけ時給が上がっているってことなんだろうけど、そばセットが850円だった頃は2000万円あれば足りると言われていた老後資金も、時給ほど年金支給額が上がるわけじゃなし、もはやそれだけじゃ日々の暮らしでおちおちそばも食べていられないってことなのだろう。
みはま食堂は厨房にスタッフが多いから、諸式高騰に加えて人件費の高騰まで余儀なくされれば、商品価格に反映されるのも当たり前といえば当たり前。
それでもやはり、もともと観光地でなおかつインバウンダーだらけの世の中になれば、価格はよりいっそう上方修正されていく。
それに比べれば都内の飲食店のほうが遥かにお求めやすい価格だったし、オタマサ実家近くの国道299号沿いの各店も、コスパ的には相当懐に優しかった。
もはや沖縄県内で価格を低めに設定するには、ヒトを雇うのではなく、家族経営&配膳ロボットを装備するほかないのかもしれない。
ヘタにヒトを雇ったら、みそ汁にネズミが入っちゃいますしね…。
あ、そうそう、オタマサ実家で思い出した。
晴れていったん自由の身となった日以来、オタマサ実家に滞在中は義弟一家に世話になりっぱなしで、せめてビールでも…と、家族それぞれが好む品を箱買いして提供していたのだけれど(それじゃ足りないけど…)、糖質ゼロにこだわる断捨離マスター弟嫁の好みは、このところもっぱらPSBだという。
PSBといえば、たしかこの冬本部町内のサンエーで、「黒」も出ているのを目にしたような記憶が…。
その話をしたところ、弟嫁は買い物の際に探したけど見当たらなかったと言い、ワタシ自身もせっかくだからお気に入りの品を進呈しようと、買い物のたびにサーチするも、ベルクは3軒、ヤオコーは2軒それぞれ回ったにもかかわらず、まったくどこにも見当たらない。
結果、
「それまで青かった缶のデザインが黒になったから、勘違いしたんじゃないの?」
と弟嫁に言われ、そう言われるとだんだんワタシもそのような気になってきて(まるで取り調べみたい…あ、一般論ですから)、結局それが結論になってしまった。
だって、ホントにないんだもの、埼玉県内のスーパーには。
ところが!
この日夕刻寄った本部のサンエーにて、ついに…

…発見!
どうだ弟嫁、これがPSBの黒だ!
< 読んでないって。
あいにくケースは無く6本パックが1つしかなかったものの、ともかく購入。
お礼第1弾として今朝野菜類詰め合わせを送っちゃったから、この証拠の品は後発第2弾で送るとしよう。
フフフ…ワタシは正しかった!
2025年03月24日
茨のたっちゃん・リターンズ。
2025年 3月23日(日) 晴れ
無風のち南の風 おだやか 水温21度
水納丸が戻ってきてからこっち、奇跡のような好天続きになっている。
その分放射冷却は凄まじいのだけれど、本土でキビシイ冬を過ごされている方は、気温2ケタもあって何を言っておるのだ、と憤慨されているかもしれない。
でも放射冷却ってのはホントに冷却機能としては高性能で、昨日ワタシが寒さに震えていた朝方なんて、南城市で氷が張ったほどなんですぜ。
気温10度で氷が張るのはなぜか。
それが放射冷却。
寒いんですって、マジで。
今日は引き続き好天ながらもその放射冷却はあるのかないのかわからないくらいで、おまけに南西の風でベタ凪ぎ、これで海に行かずにいつ行くの?ってくらいのベストコンディションだった。
これで4日連続で潜ることができる!
ところが。
9時過ぎには出動準備に入り、さあそろそろウェットスーツを着ようかという頃に、電話がかかってきた。
リョウセイさんからだ。
「今日午前中にビーチ清掃あるから出てね」
へ?
ビーチ清掃というのは、水納ビーチで営業許可を受けている3社(有限会社水納ビーチも含む)が中心となって、シーズン中に水納ビーチで営業をしている各業者さんたちがシーズン開幕前に海水浴場エリアの清掃を行う毎年恒例の催しだ。
ビーチで商売をしているわけではなくとも、とにもかくにも島の玄関口ってことで、以前は水納ビーチスタッフ以外の島のみなさんもわりと参加していたものだったのだけど、高齢化という寄る年波には抗えず、今では班長のほかに我々が都合がつけば…というくらいになっている。
今年の清掃活動主催当番であるオーシャンスタイルのオギドーさんは、きっともっと前からリョウセイさんには伝えていたのだろう。
当方はそもそもビーチで営業しているわけじゃなし、昨今の流れからするとわざわざオギドーさんが我々に伝える筋の話でもない。
そもそもリョウセイさんに伝えていれば、島内には伝わっているはず…
…とオギドーさんが考えるのは当然だ。
ああしかし、ギリギリの男リョウセイさんは、参加メンバーが乗船している連絡船到着5分前のお電話なのだった。
とはいえ連絡船到着5分前にかかってきた電話で知らされた清掃作業に参加する義理など、たとえ本島に出かける用時が無くたってまったくない…
…と、いつもだったら考えるところ。
しかし今年は、いわゆるひとつの「例の件」で世間をお騒がせした我々は、しかもこと本部町界隈に限って言えば、当時のナカイ君よりも時のヒトになっていたことは間違いない。
となれば、お騒がせしたお詫びと、とりあえず元気にしているというご挨拶をシーズン前にみなさんにする機会として、これ以上の場があるだろうか。
というわけで、「さあこれから潜りに行こう!」モードから急遽「掃除しよう!」モードに切り替え、ビーチに向かったのだった。
シーズン中は一部のビーチ業者さんたちが継続的に掃除してくれているから、台風直後でもないかぎり砂浜に大量のゴミが集積している状態をご覧になる機会はそれほどないけれど、ただ風が吹くだけの長い冬が終わる頃には、砂浜の上にはとんでもない量のゴミが溜まっている。
「海水浴場」であるがために、大雨の際などに洋上に流れ出る大小様々な流木その他自然由来のものまで除去しなきゃならないのももちろん手間ではあっても、それらはともかくも「自然」のなせるワザだから仕方がない。
それに対し、毎度のことながらウンザリするのが、ヒトのなせるワザのゴミたち。
マイクロプラスチックだなんだと、世界では(クラシカルアイの)目に見えないレベルのゴミが自然に及ぼす害も深刻になっているけれど、これだけのゴミの量を見たら、話はまったくそれ以前のモンダイであることがよくわかる。
それはまるで、救国の宰相ならぬ亡国の災相たちを初めとする政官の方々が全身全霊をかけてニッポンを滅ぼそうとしている今、「南海トラフ地震が発生したら…」などと被害予想ばかりしているようなものだ。
で、これまた毎度のことながら、集まるゴミのなかで漢字表記だけのペットボトルや各種容器の多いことといったら。
大量のペットボトルのゴミ群のうち、日本国内で売られているペットボトルは、おそらく50本に1本くらいの割合ではなかろうか(※個人の実感です)。
それでもこのようにたまにみんなで掃除をするエリアだからなんとかもちこたえているけれど、人口減少に加速度がついている今の世の中、人の手が行き届かない海岸のほうが圧倒的に多くなっているだろうから、日本全体の海岸で考えたら、溜まり続けるゴミの量はほぼ絶望的といっていい。
自衛隊を八重山の離島に配備したり、賞味期限切れ気味のミサイルを増税してまで購入する以前に、喫緊の「水際対策」が必要なんじゃなかろうか…。
まだなんとか人の手で持ちこたえている水納ビーチは、参加したみなさんのおかげで、半日の作業で見違えるようにきれいになったのだった。
午前中だけで済んだのは、コロナ禍中の数年と違って軽石除去作業が無いし、桟橋の東側は水納港関連で絶賛工事中だから、いつもの半分の量で済んだおかげだったりする。
ちょうどいつもの早お昼時間に終わったから昼食を摂り、そのあと仕切り直しで海へGO!
ただでさえお天気がいいうえに、午前中に体が温まりまくっていたおかげで、冷たい水によるダメージもさほどのことはなく、むしろ連日の好天のおかげでとうとう表層50センチが温く感じられるようになっているほどだったので、海中では快適に過ごせた。
そんな快適さがイソギンチャクたちにも伝わっているのだろうか、昨夏真っ白になって以来、昨年中はずっと白かった↓このアラビアハタゴイソギンチャクが…

…少しだけ復活し始めていた。

うっすらと茶色っぽくなってきているのがおわかりいただけるだろうか。
褐虫藻が戻ってこようとしているらしい触手を拡大してみると…

…このように斑状になっている。
サンゴにはソッコーで戻るのに対し、イソギンチャクにはなかなか戻らない褐虫藻たち、ひょっとしてイソギンチャク業界には転売ヤーが介在しているのかもしれない。
このたびようやく備蓄藻が放出されて、遅ればせながら元に戻りつつある…といったところなのかも。
住人のセジロクマノミたちはホッと胸を撫で下ろしていることだろうけれど、同じ住人のなかには「チッ…」と舌打ちしている者もいる。
この方(矢印の先)。

このアラビアハタゴイソギンチャクにたどり着いたはいいものの、先住者のセジロクマノミたちに虐げられ、日中はイソギンチャクの外にしか居住権が無いクマノミ。
セジロクマノミが住めなくなるくらいまでもっともっとイソギンチャクが弱ってしまえば…と下剋上のチャンスをうかがっていたであろうに、復活の兆しが見え始めたとあっては、引き続き日陰者生活を送るしかないクマノミなのだった。
もっとも、ここに5匹いたはずのセジロクマノミは、4匹に減少していた。
イソギンチャクが弱っていた頃に何かあったのだろう。
シメシメ…と思っているかもしれないクマノミ。
しかし触手の間をよく観ると…

…1センチに満たない激チビの姿が。
他のクマノミ類ではこれくらいのチビには市民権は与えられず、先住者の目につくやすぐさま追い払われるから、外縁部でイジけていることが多いのに、セジロクマノミの場合は大家族主義なのか、こんな小さいみぎりからイソギンチャクのどこにいてもおとがめなしという様子だった。
このチビチビが育てば、またメンバーは5匹になる。
それにしても、23度にならないと産卵を始めないはずのセジロクマノミだというのに、今1センチ未満の激チビが登場するってことは…
…いったいこのチビ、どこからやって来たんだろう?
そうやってワタシがリーフエッジでセジロクマノミと戯れていた時、オタマサは自身2度目となるレアフィッシュ(@水納島)と遭遇していた(以下の写真すべて撮影:オタマサ)。

茨のたっちゃんことイバラタツ。
前回オタマサが初遭遇したのは2021年の10月のことで、初遭遇にアドレナリンを出したまではよかったのだけど、あいにく携えていたデジイチの具合いが思わしくなく、フォーカスノブを回しても動作しなくなっていたのだった。
そのためせっかくの初遭遇というのに、引いた画角でしか撮れないという、地団駄マグニチュード8級の悔しさを味わうことに。
今回出会った子は前回よりも小さく3センチほどだそうで、幸いフォーカスノブも絶好調だったおかげで、ようやくちゃんと撮れたオタマサ。
ちなみにこのたっちゃんは、この低水温の季節ならではの(水温が上がってくると、溶けて無くなる)頼りない海藻についていたそうな。

この季節にはこのような海藻のほか、ガヤ類などが砂底からニョキニョキ出ているんだけど、それらになにかがついていたとしても見づらい見えないクラシカルアイでは目を皿のようにし続けるのがしんどいため、ワタシはよほど妖しいオーラでも発していないかぎりチェックしたりしない。
その点クラシカルアイではあっても依然視野上下左右30度の範囲だけは集中力をキープできるオタマサは、来る日も来る日も砂底を徘徊してはこのような海藻その他の付着生物を物色しているのだった。
この茨のたっちゃんとの遭遇も、オタマサにしてみればいわば必然なのである(逆に真上をマンタが通っていても気づかないのは間違いないけど)。
2025年03月23日
早すぎた春。
2025年 3月22日(土) 晴れ
無風のち南の風 おだやか 水温20度~21度
いちだんと天気が良くなって、ガメ公が日中遅くまで外に出ているほど暖かな1日になった。
ただし天気が良すぎるせいで朝方は放射冷却が激しく、室温は14度、外気温は13度と、冷え込んでいる真冬並みの絶望的寒さ。
このままだったらとても海へ行こうなどという気にはなれないところながら、さすが亜熱帯の3月、日差しは力強く、8時を過ぎればポカポカ陽気、9時を過ぎればさあ海へ!
というわけで、本日も朝から海へGO!
…という気になるくらい陸上も洋上も暖かいんだけど、ドボンと飛び込んだ海は再び20度の世界に逆戻りしていた。
満潮に向かっているタイミングなのに、なんで?
同じ20度でも、一度21度を経験した直後の20度はこれまたショックがでかい。
たった1度違うだけで、手首から先など露出している素肌部分が痛いほどになる。
これで喉元も露出していたら、小学生の頃のプールの授業後に真水のシャワーを集団で浴びせられていたときと同じく、ハフハフハフ…となってしまうところだ。
幸い、人体のうちでも体温が最も奪われる箇所といっていい喉元は、フードベストのおかげで暖かいから呼吸困難に陥ることはない。
それでも寒い…。
…と思うのはダイバーくらいのものなのか、この季節にこそ張り切る魚たちは数多い
この日訪れたポイントの砂地の根では、ケラマハナダイを初めとする各種ハナダイたちが、盛んにアピール泳ぎを披露していた。
リーフ際では、ハナゴイたちも大張り切りだ。
昨年は2月半ば過ぎから3月にかけてその様子を観ていたものだったのだけど、あいにく今年はモロモロの事情で2月は一度も潜ることができず、3月になって久しぶりに潜った時も、ハナゴイはそれっぽい動きをしていなかった。
ところがこの日は、昨年同様イエローキングたちが、メスグループを相手に盛り上がりまくり!


昨年は夏になってからもハナゴイのイエローキングに注目しようとしたところ、水温が上がってからのちは、いつどこで観てもイエローキングの姿は無かった。
おそらく季節的に今くらいから梅雨頃くらいまでがハナゴイたちの大張り切りシーズンで、なればこそ尾ビレを黄色く染めてメスへの大アピール大会になっているのだろう。
ちなみに昨年も紹介したように、イエローキングが尾ビレを真に黄色く染めているのは、メスに対して激しく泳ぐときだけで、いわば束の間の興奮色。
なのでアピール泳ぎのインターバルには、尾ビレは褪せた黄黄色になる。
かといってアピール泳ぎをしている際は、動きが激しすぎて撮れたものじゃない。
となると、イエローキング状態を捉えるチャンスは、メスへのアピール泳ぎが終わった直後、まだヒレを広げて余韻に浸っているわずかな間しかない。
そのため、オスたちが張り切っていないときはなかなかチャンスが無いのだけれど、この日はタイミングが良かったのかどのオスも絶好調だったから、数撃ちゃ当たる的に遊ぶことができたのだった。
水温20度のせいで寒さに震えていたはずなのに、ハナゴイ相手に遊んでいたおかげで気がつけば寒さを忘れていたほど。
ダイコンの水温表示を見ると、21度になっている。
もしかして、夢中になっていたから水温上昇?
ハナダイやハナゴイたちが盛り上がっている一方、リーフエッジ付近では、このところキホシスズメダイたちもアヤシイ集団となっている。
繁殖行動を伴うキホシスズメダイの集団行動についてはこちらをご参照いただくとして、ダイバーの存在すら目に入らなくなる彼らの群れの動きは、まさに春ならではのもの。
すでに産卵床でメス待ち態勢になっているのか、すでに産み付けられた卵を守っているのか、群れとは行動を別にして巣穴付近に陣取っている黒いキホシスズメダイの姿も数多い。
そんななか、リーフ下のサンゴ群にふと目をやると、まさかの…

…キホシスズメダイチビターレ。
あまりにも……早すぎなくね?
このチビのフライングっぷりを物語るかのように、周辺4メートル四方を見渡しても、そして本日の1本を通しても、キホシチビはこの1匹だけ。
単独で暮らす系のレアチビチビならともかく、季節ともなれば湧き出でるがごとき巨群になる彼らチビターレなのに、たった1匹って…。
視聴率ではアルプスの少女に惨敗、そして1年間の放送予定が半年に短縮されて終わってしまった「宇宙戦艦ヤマト」と同じくらい、世の中への登場が早すぎたかも、キホシチビターレ。
世が世なら↓このメンバーの一員になれたろうに…
…サバイバル的に、後続を待ち続けるのは厳しかろうなぁ。
2025年03月22日
もぬけのギャランドゥ。
2025年 3月21日(金) 晴れ
北の風 少し波あり 水温21度
今日はさらにいいお天気に。
朝からお日様が出ているおかげで、午前中の早いうちに体が温まってきた。
これなら10時前でも海に行けそうだ。
さっそく本日も海へGO!
2日続けて海へ行くだなんて、いったいいつ以来だろう…。
洋上にはダイビングボートが数隻停まっている程度だったから、どこかしらにボートを停めることはできそう。
せっかくだから前日とは違うところへ…
…と思ったものの、どうせだったらその後のケラマハナダイの様子を観ておきたい。
というわけで、再訪。
はてさて、ケラマハナダイのメスたちの様子は…

たしかにこのようにお腹パンパンな子もいるにはいるんだけど、その数が前日ほどには目立たず、おおむね↓こんなくらいだった。

これだと、普段どおりって感じ。
オスの動きも昨日ほどではなく、張り切って急降下泳ぎをしているのは1~2匹くらいのもので、むしろキンギョハナダイのオスたちのほうが俄然張り切っているように見えた。
やはりこのたびのローテーションの盛り上がりのピークは、昨夕だったってことなのかなぁ?
砂底に目を転じると、そこかしこにベラギンポの仲間が砂底上にチョコンと鎮座していた。

リュウグウベラギンポなら、季節になると砂底の上50センチほどのところで群れを作るので、遠めでもその存在に気づくことができる。
盛り上がっていない今のような季節には、リュウグウベラギンポであってもそれぞれが思うままに砂底で暮らしているらしい。
だからといってどこに行けば必ず見られるという魚ではないんだけど、どういうわけかこの根の近くでは大小各サイズのベラギンポをたくさん観ることができる。
もっとも、このように画像だけ見ても、ただ細長い魚がそこにいるだけでしかないからつまんない。
彼らの本領は、その動きにある。
ベラギンポたちは、スーパー高速砂遁の術師たちなのだ。
その様子をコンデジ動画で撮るのは至難の業ながら、かろうじて彼らの術がわかるくらいには撮れた。
これくらいの大きめの個体だと、砂中に潜ったあとチョロッと出ている顔が見えるからどこにいるかがわかりやすいのだけど、もう少し小さな子になるとずっと観ていても見失ってしまうほど。
でもこちらが場所を把握していなくても、近づいていくとプレッシャーに負けたベラギンポはすぐさま砂中から飛び出て居場所を教えてくれるのだった。
さてさて、昨夏の白化騒ぎも過去のものとなり、かろうじて死を免れたサンゴたちが今度はシロレイシガイダマシの集中砲火を浴びるという、新たな禍の時代になっている現在、頑なに白化を堅持しているものたちもいる。
イソギンチャクたちだ。
先日もお伝えしたように、すでに年間最低水温に達しているというのに、いまだに白いままのものたちがあまりにも多い。
このポイントの水深20メートル弱の根にいるウスカワイソギンチャクときたら、白いままのうえに縮みまくっていた。

これじゃあペアでは暮らせなくなっているのだろうなぁ…。
そうかと思えば、同じ根のもう少し上方でデデンと育っているタマイタダキイソギンチャクは…

…濃すぎだろッ!と思わずツッコミたくなるほどに、必要以上に褐虫藻が入ってしまっているように見えた。
昨夏でもこの水深くらいあるところなら、ほとんどのサンゴたちは災禍なく暮らしていたというのに、イソギンチャク類の場合はもっと深いところでさえ白化しているものがけっこう観られる。
なぜイソギンチャクだけ?
リーフ際でも無事なものは無事、ヤバいものはヤバいという具合いでその差が大きいのだけれど、ヤバいものは相当ヤバくなっている。
イソギンチャクが元気なころは、お舟さんとおかるさんほどの距離感でコミュニケーションをとっていたクマノミとハマクマノミたちだったのに…

昨夏以来イソギンチャクが白いままで、なおかつ縮んでしまっている両家の間では、現在塀越しの会話もままならなくなっている。

↑ここからほど近いリーフエッジで長い間ずっと観てきた↓このハナビラクマノミが暮らすシライトイソギンチャクも…

…昨夏順当に白くなって、その翌日あんなことになるなどとは夢にも思っていなかった今年1月20日には、限界1歩前くらいにまで縮んでしまっていた。

その後どうなったか、様子を観に行ってみたところ…

…もぬけのギャランドゥ。
こうなることを予期していたわけじゃないから、同じアングルから撮っていない画像でわかりづらいとは思うけれど、この場所で2016年の白化もちゃんと乗り越えたシライトイソギンチャクは、ハナビラクマノミともどもついに力尽きてしまったようだ。
それにしても、生き残ったサンゴたちにはちゃんと褐虫藻が戻っているのに、なんでイソギンチャクには元気を取り戻しているものとずっと禍を引きずったままのものがいるのだろうか。
高水温に苛まれていた夏場でも、リーフエッジ付近のほぼ同じ水深でほとんど同じ環境にいる同じ種類のイソギンチャクが、一方は完全白化、一方は何の変化も見せないってこともあった。
サンゴが白くならない深いところでも白化するし、水温がガクンと下がって随分経つというのに白いままのものが多いし、それどころか今なお死に向かっているものすらいるイソギンチャクたち…というのは、今回の白化に限らず、98年の大規模白化でも2016年の中規模白化でも同様だった。
無事なものは無事でいるだけに、なんだか並べられている椅子よりも子どものほうが少ない椅子取りゲームのよう。
このあたりのことについて、アカデミズムの世界ではすでに明確な説明がなされていて、立て板に水のごとき解説をしてくれるオーソリティがいらっしゃるのだろうか。
ご存知の方、テルミープリーズ!
2025年03月21日
アツさに乾杯。
2025年 3月20日(木) 曇りのち晴れ
北の風 やや波あり 水温21度
風はすっかりおさまって、ようやくまずまずの海況になってきた。
今週初の海日和だ。
でも朝から雲が多く、午前中は気温が低いままだから、せめて体が温まってからにしようってことで、早お昼を済ませてから海へGO!
先日は水温のあまりの低さに打ちのめされたけれど、この日はワタシのダイコンの水温表示的には1度上昇していて(小数点以下1ケタまで出るオタマサのダイコンでは0.6度上がっていたらしい)、前回に比べるとドボンと飛び込んだ際のショックは随分小さかった。
23度以下の水温では1度ごとの違いが大きいということは過去に何度も触れているとおりで、20度と21度というたった1度の差は、アームストロング船長の1歩と同じくらいとてつもなく大きい。
しかも23度から21度に下がるのとは違い、年間最低水温からの上昇となれば、勇気凛々元気百倍、意気衝天の絶好調!
…ってほどではないにしろ、とにかくエントリーと同時に戦意喪失ってことにはならずに済んだ。
そのおかげか、小さな小さなブルマちゃんの存在に気がつくことができた。

尾ビレの先の透明な部分を除いたら1センチほどしかないチビターレ、例年この時期に観られ始めるのだけれど、どういうわけか昨年は激チビには出会えなかった。
それがこの日は、このあと別の場所でもう1個体とも遭遇。
例年に比べて分母が限りなく少ないにもかかわらずこの遭遇率、ってことは今季は数多いのかな、ブルマちゃん=キツネベラ。
ブルマちゃんの近くには、長さ40センチほどとやけに短いムチカラマツに、ガラスハゼがついていた。

このムチカラマツは以前も何度か紹介しているもので、一昨年の今時分はこんな感じになっていた。

黒くなっているところはガラスハゼがサンゴの共肉を剥がして産卵床にしている部分で、この時にはすでに卵が産みつけられている。
で、以前も紹介したように、ガラスハゼは同じ産卵床を手入れをしつつ繰り返し使い続けるんだけど、産卵のピークが過ぎて周期が長くなると、環境が整ってさえいればムチカラマツは剥がされた部分を修復する。
なので↑この2ヶ月後には、↓こうなっていた。

ジワジワ修復進行中。
そしてその翌年、すなわち昨年1月には↓こうなっていた。

ほぼ完全復活。
ただしこの頃にはガラスハゼペアの姿は無く、ただの短いムチカラマツになっていた。
やっぱ、ペアが暮らすには短すぎたか、ムチカラマツ。
ところがこの日このムチカラマツには、再びオトナサイズのペアが復活(ムチカラマツの根元のほうにもう1匹いた)。
近くにムチカラマツが生えているわけじゃないから、別のムチカラマツと行き来しているわけではなさそう。
ってことは、昨シーズン中知らないうちにチビチビガラスハゼがやってきて、そのまま成長したのだろうか。
産卵床が見当たらないところをみると、ひょっとすると比較的最近、新天地を求めて遥か遠くからわざわざやってきたペアとか?
この先このペアはどうなるのか、今年はもう少し注目してみることにしよう。
このムチカラマツがある根では、ハナダイ類のオスたちが盛んにメスにアピールしていた。
高所からメスのところへ急速降下し、なにやらメスにアピールするや、すぐさま元の場所に戻るこの動き、ゲストをご案内中にはしつこいくらいにご覧いただいていたから、きっとご存知の方も多いことだろう。
当店ゲストだったにもかかわらずいまだご存知ない、記憶にないというフトドキな方のために、その様子を拙い動画で。
アピール泳ぎをしているときでも、カメラを向けると嫌がってやめちゃうことが多いのだけど、この日のオスたちはやけに張り切っていた。
張り切っている時のオスは、1匹が何度もこの張り切り泳ぎを繰り返すものだから、群れ全体で見るとハナダイたちの雨あられって感じになる。
いつもに比べ、ケラマハナダイのメスたちが妙に思わせぶりだったので注目してみたところ…

あらら、お腹がパンパン。
どのメスもみな似たようなお腹をしているところをみると、きっと産卵が近いのだろう。
なるほど、オスが張り切るわけだ。
最近加筆修正したばかりのケラマハナダイの稿で紹介しているように、早くも…というか遅くもなのか、とにかく寒い1月から熱いバトルを始めているケラマハナダイたちは、どうやら(海中の)冬に産卵しているっぽい。
おそらく産卵は日没前後なのだろうけど、こんな寒い季節のそんな時刻に潜るほどワタシはアツくはないなぁ…。
ケラマハナダイのオスたちのアツさに乾杯。
そのアツさのおかげで、毎年梅雨前後から各根にチビターレたちがたくさん出現し始めるのだ。
ここ20年で大幅に減少傾向のハナダイたち、もっともっと頑張って、産めよ増やせよチビターレ。
2025年03月20日
広がる患部。
2025年 3月19日(水) 曇りのちちょい晴れ
北の風 荒れ模様のち波あり
風がおさまる予報になっていたこの日、代船はまかぜ号が運航するとなれば、連絡船用バースに避難させているうちのボートを朝から定位置に戻さなくてはならない。
おさまる予報とはいっても、朝はそれなりに風があったから、それはそれで面倒だなぁ…
…と思っていたら、水納海運公式ページには全便欠航を告げる表記が。
ラッキー♪
明日はようやく水納丸がドックから戻ってくる日。
10日間の代船運航が予定されていたはまかぜ号、最初の4日間は「手続き」のために欠航、後半は時化の連打で、結局10日間のうち運航したのは数日だけになっちゃった。
今日は運航しないとなれば、ボートを定位置に戻すのは翌日でいいか…
…なんてのんびり構えていると、いつぞやのように連絡船が到着する直前まで忘れていてえらいことになったりしたら大変なので、夕刻に戻しておくことにした。
この日の夕刻くらいなら大したことはないけれど、防波堤の西側が無くなってしまったから、今後は同じ北風でも桟橋脇に達する波の威力は違ってくるのだろうなぁ。
そうそう、この日は午後3時のコーヒータイムのときにもすでに晴れ間が出ていたから、久しぶりにデッキの上でお茶をしていたときのこと。
突如オタマサが素っ頓狂な声を上げるのでナニゴト!?と思ったら、ヤツガシラが裏の未舗装路に舞い降りてきたのだった。
デッキ上の我々が居るところから、ほんの5メートルほどの距離。
近すぎたあまりオタマサの声でビックリしたヤツガシラは、直ちに飛び去って、チェッカーフラッグのような羽の模様をたっぷり見せてくれたのだった。
何度も言うけど、家に居ながらにして、なおかつコーヒーを飲んでいるときに、ヤツガシラを目と鼻の先のところで観られるだなんて、ああ、なんてゼータク。
ニッポンにはそういうゼータクがいくらでもあったはずなのに、オキナワをはじめとする各地は、なんだか全力でそういったゼータクを一掃しようと励んでいるようにしか見えない。
その昔の子供の頃、高齢者が暮らしの端々で折りに触れポツリとつぶやいていたことばが、今になってよぉ~くわかる。
「昔はよかった……」
話は変わる。
今メインで使っているノートPCは、元々は外出時の携帯用であったりスーパーサブであったりしたもので、昨年1月にPCを押収されちゃったから急遽出番出来となったもの(そのPCは先日ようやく回収できたのだけど、オタマサ実家に置いたまま…)。
むしろサブのほうが高性能だから、持っていかれたハードディスクの中身が無いということ意外は特にモンダイはなかったんだけど、使用頻度が急に増したためか、それまで大したことがなかった症状がこのところジワジワと進行し始めている。
その症状とは、これ。

以前までは液晶の隅の隅がちょっとだけ欠損している程度だったものが、使用頻度が増して1年使っているうちに↑こうなってしまった。
だからといって急速に拡大していくわけではなく、↑これからひと月経った現在でも↓この程度。

これって、液晶の液漏れなんですかね?
見るからに「今後さらに広がります」という固い意思を見せている気はするけれど、とりあえず今のところ使用するうえでモンダイはない。
だからといってこういうものは虫歯と一緒で、放っておいてもけっして良くなることはなく、症状は進む一方なのだろう。
で、最終的にはどうなるんでしょ?
世間にはこういう症状を直す業者もたくさんあるようながら、実際に直すとなるとけっこうな料金になるっぽい。
すでに購入後7年近く経っている2018年モデルなんて、同等のものなら5~6万で買えそうなもの。
それを何万円もかけて修理するってのもなぁ…。
バカバカしいから今のところは様子を観ているだけなんだけど、実はお安く解決できる方法があったりするんでしょうか。
それとも、どのみち放っておいても他のモンダイで寿命を迎えるほうが先…ってくらいのものなんでしょうか。
お詳しい方、テルミープリーズ!
2025年03月19日
ヤツもいた。
2025年 3月18日(火) 曇り少し日ざし
北の風 うねりあり
一昨日昨日と欠航が続いていたはまかぜ号、きっと今日も欠航だろうと予想していたところ、意外にも朝イチ便のみ運航ということに。
朝イチだけだと買い物に出かけても帰ってこられないから、島民にとってはほとんど意味がないのだけれど、郵便物が出せるという特典(?)はある。
それに我々の場合、本島に出られさえすれば、渡久地港に避難中の自分たちのボートに乗って帰ってくるという手段がある。
午後になって風が強まってきそうとはいっても、正午過ぎくらいまでは大丈夫そうだったから、朝イチ便で出掛けることにした。
というわけで、この日クリーニングが仕上がる予定だった上着の受け取りや、ゆうパックや郵便物の発送、各種支払いも済ませることができ、欠航続きでヤキモキする必要もなくなったのだった。
ただし、帰りは波しぶきの洗礼を浴びることになったけれど…。
実はこの欠航続きの間、チーム電車でGO!A木総裁が水納島にご滞在予定だったのだけど、あいにくの荒天のために望み叶わず。
いらっしゃったからといって我々が何をどうこうするわけでもないものの、1月の例の件の際にはご旅行先でニュースを知ることとなり、たいそうご心配をお掛けしていただけに、この時期ならではの野菜料理を宿に差し入れするくらいのことはできるはずだったのになぁ。
一方総裁は総裁で、我々にお土産を手渡そうとしてくれていたそうなのだけど、それもかなわず…
…となるところ、今日朝イチ便だけでも動くのであれば、せめて15分滞在で島に行こうと思っていたらしい。
ところが我々は島から出る予定だったので、いっそのこと渡久地港でお会いすることに。
定刻より遅れること30分、ようやく渡久地港に到着すると、いつもと変わらぬ総裁の姿がそこにあった。
彼は去る1月再び南アフリカまで「帰省」をしていて、その帰省中にいろいろお土産を仕入れてくれたという。
そのひとつがこちら。

南アフリカのビール!
ちょっと気の利いたスーパーにさえ世界各地のビールがズラリと並ぶ世の中になってはいるとはいえ、南アフリカのビールにお目にかかる機会などまずない。
その昔ケニアで堪能した(そして1ケース買って帰った)タスカービールもたいそう美味しかったけど、はたして南アフリカのビールやいかに?
せっかくだからこんな寒い日ではなく、もっと暑くなってからいただこうっと。
寒い時でもOKなものもいただいてしまった。

BILTONGと書いてビルトンと読むそうで、その昔大航海時代の保存食需要から生まれた干し肉のことだそうな。
南アフリカをはじめとする南部アフリカ諸国では同じみのものだそうで、ジャーキーなのかなと思ったら、砂糖は使わず酢を使ったり、燻製はしない、薄くスライスしないなどなど米国のジャーキーとは作り方もひと味違っていて、まったく別モノであるらしい。
鶏肉を使えばチキンビルトン、牛肉を使えばビーフビルトンということになるこのビルトン、いただいたこのビルトンははたして何ビルトン?

ん?KUDU??
なに、KUDUって。
デザインされている絵柄を見るかぎりでは、レイヨウ系の動物に見えるけど、どんな姿をしているんだろう?
というときのために(ってわけではないけれど)、総裁はこういうものも用意してくれていた。

今回の「帰省」では電車でGO!が「サファリでGO!」になったそうで、探訪されたクルーガー国立公園の地図もお土産に。
地図といいつつ広大な国立公園内で観られる野生動物がたくさん紹介されていて、このKUDU(クドゥもしくはクーズー)もしっかり載っていた。

グレーターってくらいだから相当でっかいようで、現地ではかなり存在感を放っているっぽい。
でもヌーにもウシカモシカという和名があるくらいだから、きっとこのKUDUにも和名がついているはず。
調べてみたところ、彼らの名前はネジツノカモシカ(ネジツノレイヨウ)だった。
ちなみにカモシカを漢字で書くと羚羊、音読みにするとレイヨウになります。
たしかに角は盛大にねじれてはいるけれど、サバンナにおける存在感からすると、なんだか冴えないその名前…。
やっぱKUDUのほうがカッコイイか。
そんなKUDUのビルトンをさっそく実食!

これは……
美味いッ!!
スパイスが効いたジビエの干し肉は、琥珀色のお酒にスペシャルマッチング。
今思えば、その昔アラスカの寒村でいただいたムースの干し肉、当時はジャーキーとばかり思っていたけれど、あの分厚い干し肉はむしろビルトンだったのかも。
現地でいただいたムース(ヘラジカ)の激ウマ度合いを思えば、きっとビルトンも現地で食べればさらにさらに至宝級なのだろうなぁ…。
A木総裁、貴重な味覚体験をさせていただきありがとうございます。
ところで。
さきほどのクルーガー国立公園の地図に掲載されている各種野生動物たち、そのなかにはこんなのも紹介されていた。

アフリカンフーポーとはもちろん、ヤツガシラのこと。
日本本土では珍鳥扱いのヤツガシラだけれどその分布域はかなり広く、古代ローマ帝国とペルシャ帝国とモンゴル帝国とムガール帝国とクメール王朝にアフリカ大陸を合わせたほどの、広大な版図を誇っている。
かつて何かのドキュメント番組で、ヤツガシラがイスラエルにもいることを知って驚いたことがあったっけ…。
ただ、昔は1科1属1種の鳥として紹介されていたはずなのに、ウィキペディア的情報によると南部アフリカにいるものとマダガスカルにいるものは、それぞれ「別種」ということになっているみたい。
そのため英語名的には、我々が水納島で観ているものはユーラシアンフーポー、マダガスカルにいるものはマダガスカルフーポー、そしてクルーガー国立公園で観られるものは、アフリカンフーポーということになるのだそうな(渡りをするのはユーラシアンだけらしい)。
ま、分類学的には3種の間に微妙な違いがあるにせよ、その姿は紛れもなくヤツガシラ。
水納島のような小さな島で観られる鳥さんが、遥か南アフリカにもいるというこの不思議…。

ヤツはなにげにインターナショナルなのである。
いや、A木総裁のことじゃなくて…。
彼ら電車でGO!が、クルーガー国立公園で「ヤツガシラよぉ~し!」と指さし確認をしたかどうかは知らない。
2025年03月18日
ヤツが来た。
2025年 3月17日(月) 雨のち曇り少し日ざし
北の風 荒れ模様
前日からずっと冷たい風が吹き続けているから、本日は朝から冷え冷え。
室外の寒暖計は15度のまま微動だにせず、これで風の当たるところに居たら、体感気温は10度くらいに違いない。
なので暖房をつけて部屋でヌクヌクしていたところ、ふと見やった北側の窓の向こうに、あの姿が!
これはチャンスとばかりカメラを手にし、窓ガラスと網戸越しに無理矢理撮ろうとしたところ、あと一歩のところで飛び去ってしまった。
はて、こちらの気配はバレていないはずなのに(網戸越しだと、よほど近づかないかぎり見えないらしい)、なんでだろう?
…と思ったら、脇からカニステル収穫のためにナリコさん登場。
というわけで証拠写真は撮れず。
しかしこうなるとチャンスを自ら求めたくなるもの。
さきほどまで一歩も外に出る気にはならなかったというのに(オタマサは例によってどこかでゴソゴソしてはいるけど)、コンデジ片手に外をうろついてみることにした。
すると、上空を鳥の大群が横切っていった。

数や1羽1羽のサイズからして、ムナグロかな?
近年は毎冬ごとに防波堤や桟橋、ビーチあたりを根城にして居つくことが恒例になっていたムナグロたちながら、今冬は防波堤があんなことになっちゃってるから、のんびり過ごしていられるはずもなし。
もう観られないかなぁ…と思っていただけに、上空通過だけとはいえよかったよかった。
いやいや、この寒さの中で歩いているのは彼らのためではなかった。
だからといってそうそう遭遇できるものではない…
と思いきや、ちょい遠めの電線の上に…

ヤツがいた。
これまで2羽以上いることは滅多になかったから、先ほど窓越しに見た子でまず間違いないだろう。
樹上にいるのは過去に観たことがあったけれど、電線上は初めてかも。
のんびり落ち着いているようだったから、もう少しちゃんと撮ろう…
…と思ったら

飛び去っちゃった。
なんで?
すぐそばの電柱の天辺に、ガラサーが舞い降りてきたのだ。
カラスはカラスでちゃんと縄張り意識があるらしく、見慣れぬ新参者が来ると圧力をかけるのである。
昼の散歩では姿を見掛けなかったので、ひょっとするとカラスがイヤで遠くへ行っちゃったのかも。
午後遅くには日も出てきて、気温は変わらずとも見た目暖かそうだったから、再びコンデジ片手にヤツを求めて彷徨ってみた。
すると、どこからともなくヤツが未舗装路に舞い降りてくれた。

でも遠すぎるし、草は丈高いし、だからといって身を隠せる場所がないからこれ以上近づけないし…
…と思っていたら、そこからすぐ近くのヘリポート用広場まで飛んだヤツガシラ。

しばらくジッとしてたけれど、本来こういうところが大好きなヤツのこと、すぐにエサを探し始めた。
この様子なら、何かをゲットして食べる様子や、冠羽全開も観られそう…
…と思ったら、そこへ午後5時のドボルザークが。
東日本大震災を機に非常時用に整備された各地域ごとの放送設備、水納島の場合それが非常時に活躍したことは一度もないものの(使われてはいても役に立ってないという意味で)、非常時のみ使用ってことにするといざという時使えないかもしれないから、正午や夕刻の時報変わりの音楽や、役場の放送などで使われている…というのは全国各地と同様だ。
ただし水納島の場合は1か所のスピーカーから島全域まで聞こえるように…とのことから、とてつもない大音量に設定されている。
コーラルリーフさんにお泊りの方ならご存知のとおり、スピーカーの直下にいると「気でも狂ったか?」ってくらいにうるさいから、心臓が悪い方なら時報代わりの音楽が始まった途端心停止してしまうかもしれない。
スマホを携帯していること前提で動いている世の中なんだから、そういう地域ごとの緊急放送もJアラートのようにスマホで済ませればいいじゃん。
「高齢者はそういうわけには…」
じゃあその高齢者の心臓に爆音放送がトドメをさすかもしれない…ってのはどうなのよ。
ともかくそういうわけで、ヘリポートあたりでも時報代わりのミュージックは相当な音量で、せっかくのんびりエサ探しをしていたヤツガシラも、ビビッて飛び去ってしまった。
この少し前に、オタマサもジョギング中にヤツが飛び立つところを観ることができたそうな(ヘリポートの傍にどこからともなくヤツが舞い降りてきたのは、おそらくそのタイミングだったはず)。
工事の音はするわ放送はうるさいわで、ヤツにとって落ち着かないこと甚だしいだろうけれど、とにもかくにも今季も姿を見せてくれたのは、ひとえにまだ島内で工事が始まっていないからこそ。
昨年が見納めかと覚悟をしていたというのに、ヤツガシラ遭遇チャンスにも1年の猶予を与えてもらえたのは、これすべて港のグダグダ工事のおかげでございます。
2025年03月17日
北風小僧がささやいた。
2025年 3月16日(日) 雨のち曇り
北西の風 時化模様
夜のうちに風は北に回り、冷たい空気が大量に運ばれてきた。
3月も半ばというのに、冬に逆戻り。
機能停止級ってほどではないにしろ、強風吹きすさぶ中ずっと風に当たりっぱなしでいたら、きっと心臓は停止してしまうことだろう。
以前も触れたように、3日もあれば人間の脳は環境に適応するというのはまことに不思議なもので、今月6日に一時帰沖のつもりで秘密基地まで戻ってきた夜、シャワーからパンイチで出てきてもまったく寒さを感じなかった。
やっぱ沖縄は暖かいなぁ…
…と思っていたところ、寒暖計を見たら16度しかない。
フツーだったら暖房をつけるかどうかという低温だというのに、気温ヒトケタの世界に適応していた脳には、16度はたいそう暖かかったのだった。
もっとも、それを暖かく感じていたのは束の間のことで、翌朝にはすっかり元に戻ってしまった。
脳が元に戻るには3日も必要としないらしい…。
帰沖後10日も経つと、この日の気温でもけっこう寒い。
~♪
北風小僧がささやいた
息が白く弾んだら…
今夜は 今夜は~~~
オタマサおでん♪

今冬も絶好のおでん日和が何度もあったものの、あいにくずっとおでんどころではなかったために一度もチャンスが無かった我々だから、これが今季初おでん。
いったい何人家族なんだ?ってくらいに大量の具材をでっかいお鍋で朝から煮込んでいただけあって、直径10センチはある大根すら握力5しかないヒトでもお箸で取り分けられるほどで、これがまた美味しいんだわ。
どうせなら大根は裏あたいで成育中のオタマサ産で…と予定していたらしいのだけど、あいにくの雨。
大根のためにずぶ濡れになるのもバカらしい。
そんなときでも心配御無用、冷蔵庫にはリョウセイさん大根の備蓄もたっぷりなのだった。
ちなみに沖縄のおでんに欠かせないレタスはヒミツの畑産で、オタマサによると先日出掛けた際にはまだちょいとばかり収穫するには早いくらいだったそうなのだけど、このように欠航が続く見込みだったから、ちょい早めでも収穫してきたモノ。
いまだにレタス入りおでんを試したことがない方、これがけっこう合うんですよ、ホントに。
野菜といえば、副菜プレート。

ブロッコリーはトシおばさんから、カリフラワーはナリコさんからそれぞれいただいたもので、実はどちらもオタマサがお裾分けした苗が育ったものだったりする。
いわば逆輸入ながら、同じ苗がほぼ同じ島の土壌で育っているだけに、美味しさもまったく同じ。
調味料など何もつけずとも、蒸すだけでなんとも甘い蕾たち。
でもちょっと味変したいときには、バーニャカウダなどいろいろとあるなか、最近ヒトからいただいた↓これもなかなかいけますぜ。

すでにけっこう使用しているので、表面デコボコですみません…。
おフランスの東部地方では「夏でもチーズフォンデュ―を食べたい」というワガママなヒトが多いらしく、その需要に応えるべく昔からその地方ではこういうもの(カンコワイヨット)が作られているのだそうな。
なんでもかんでも手の込んだ調理をしてソースや何かをかけなきゃ気が済まない方々だから、きっと蒸しただけの野菜の旨さなど知る由もないんだろうけど、なんでもかんでもかける文化だけにこれはこれで美味しい。
スーパーのブロッコリーでも、ちょっとした高級野菜に変身するかも。
ところで、さきほどの野菜プレートに慎ましく載っているトマトは…

プチと中玉のローストトマト。
これまた先日ヒミツの畑からオタマサが大量に収穫してきたもので、半分にカットしたものをズラリと並べてローストしたこの時期恒例のオタマサスペシャルだ。
ローストして余計な水分が出た後のトマトが、またスペシャル級の甘さ。
甘いといっても甘味料のようないやらしい甘さではなく、爽やかな春の風のような心地よい甘さだから実に美味しくいただける。
昨夕はこれを大量に使って…

…春のパスタ♪
まったくもう、雨降りばかりでろくろく運動もできないというのに、美味いもん食ってばかりいるワタシはどうしたらいいのだ。
< 知らねーよ。
2025年03月16日
グッジョブ、グダグダ。
2025年 3月15日(土) 雨のち晴れ間
南西の風 けっこう波あり
朝から雨模様、それも本降りだから、屋外で何かをしようなんて気にはまったくならない1日に…
…なるかと思いきや、昼過ぎには雨が止み、午後遅くには晴れ間すら広がった。
旅行者には絶望的な週末になるかと思われたけれど、日中にお日様が出たし、今日のところはまだ南風だったから気温も暖かいままで、それほどの大ハズレにならずにすんでよぉござんしたね。
我々にとっても今日のところは気温が高いままでいてくれたのは良かったのだけど、雨模様だから洗濯物を外に干せず、なおかつ湿度が高いし風も通せないから洗濯物が全然乾かない。
扇風機でもあれば風を当て続けてってこともできたろうに、そんなものは無いからエアコンを使う…
…にしても、室温24度で暖房を使っても意味がないから、温度設定高めで除湿をかけた。
すると、室内だけ先月に戻ってしまった…。
外に出れば暖かな春だというのに、室内にいるにはシャカパン&上着がいるだなんて…。
これが本島なら、そこらじゅうにあるコインランドリーで、乾燥だけチャチャチャと済ませられるのだろうなぁ…。
そんなバカバカしい寒さに見舞われはしたものの、雨が止んだ午後からオタマサは例によってゴソゴソ開始。
そして表あたいは、夏バージョンに衣替えをした。

オクラ、シシトウ、ナス、ピーマンといった面々。
苗それぞれをビニールで囲っているのは、けっして風避けというわけではなく、若い苗を好んで食べるヤドカリ避け。

海辺にお暮しではない方々には意外だろうけれど、庭にフツーにヤドカリがウロウロする小さな島では、育ち始めの野菜たちがけっこうヤドカリの被害に遭うのだ。
こうしておけば、ヤドカリ被害に遭うことも…
…ないはずなんだけど、なにしろ施工者はオタマサなので、頑張るヤドカリなら侵入できてしまう作りだったりする。
なのでせっかく手間暇かけているくせに、必ず苗の1本や2本は被害に遭うゆる~いヤドカリ対策なのだった。
雨のためにいつものお昼の散歩はできなかったかわりに、雨が止んでからオタマサがゴソゴソしている間に、ちょっとばかし歩いてみることにした。
アテもなく彷徨おうとしていたところ、先だっての謎の鳴き声改めリュウキュウヒクイナの声がしたので、かなわぬまでも近づいてみることにした。
ちなみにリュウキュウヒクイナの声は、その後朝夕に全然声がしなくなって、てっきりもう居なくなってしまったものとばかり思っていた。
ところがブランク1日半くらいで、再びキョキョキョキョキョ…という声が戻ってきた。
雨のおかげだろうか。
声はすれども姿は見えず…のリュウキュウヒクイナ、この時はまだ日が高い時間帯だったからか、1度鳴いただけで沈黙してしまった。
遠く草っ原に鳥がいるのが見えるたびに、さては…もしや…と注視してみるものの、それはハトであったりシロハラであったりして、まったくクイナの気配はない。
ところが、そろそろ帰ろうかと思ったその時、タツヤさんのおうち近くの未舗装路上に、首長めの茶色い鳥さんの姿が。
これは!
すぐさま写真を撮ろうとした動きをした途端、首長めの赤茶色バードは、滑るように走って藪の中に消えてしまった。
50メートルは離れていたというのに…。
その警戒心と緊張感は、現農水相の1万倍くらい高い。
それはともかくそのフォルムといい走り方といい、これはどう見てもクイナ系。
そしてシロハラクイナよりも2周りほど小さく、赤茶色のボディとなると、その正体は…
リュウキュウヒクイナ!
ついに初遭遇♪
…写真はないけど。
こうして路上に姿を見せることがあるとわかれば、まだこの先チャンスがあるかもしれない。
午後遅めには、晴れ間も出てきたことだしガメ公のエサ採りを兼ねて散歩することにした。
本日は牛小屋方面へ。

昨年4月に催されたリゾート開発の説明会では、早くも年明け早々にこちら方面の工事が開始されるという話だった。
だからこそ昨夏には、人工物がほとんどないこの景色もこれで見納めですぜと紹介したのだけれど、年が明けても2月になっても3月になっても、いっこうに工事が始まる気配がない。
これはひょっとしてポシャッちゃったかな?と淡い期待を抱きそうなところながら、どうやら開発業者の都合というよりも、遅々として進まない港の工事の進捗状況に影響されているのでは。
そう思っていたところ、先日の水納港の工事の説明会において、リゾート開発業側の立場で今後の工期について質問が出た。
グダグダの北部土木事務所都市港湾斑に来年度以降の「今後」を訊いたところで、具体的な返事を期待するのは土台無理な話ながら、その質問者のおかげでリゾート開発の工事開始予定が来年からであることがわかってしまった。
住民説明会を開いて「来年から」と言った予定が大幅に変わるのであれば、それについても「説明」しろよ開発業者。
もっとも、「住民」のみなさんとの懇親会では、そのあたりについてもちゃんと語られているんだろうけれど。
それはともかく、来年からということは…
今年はまだ工事が始まらない!
昨年の段階では、今年早々に牛小屋方面の道には立ち入れなくなり、現行の桟橋は使えなくなる…という状況だったものが、どちらも1年の猶予がついたのだ。
本来の予定どおりになっていれば、とてもじゃないけどここで暮らしていけないから、今年は静かにフェードアウト…というつもりでいた。
ところが1月からご存知のとおりの状況になって、自分たちの身もままならないところへもってきて、さんざんご心配をお掛けして迷惑も掛けて留守中には世話になって、それで工事が始まったから「じゃ!」ってわけにもいかないなぁ…
…と思っていたところ、猶予のおかげでとりあえず身の処し方を慌てて考える必要は無くなったのだった。
グダグダズルズルな港の工事、グッジョブ。
2025年03月15日
独眼竜X。
2025年 3月14日(金) 曇りのち雷雨のち曇り
南西の風 おだやか
本日ようやく代船はまかぜ号が現場復帰!
…午後からだったけど。
日曜日にはけっこう時化そうで、なおかつ水納港は工事の作業船の都合でいつも避難場所にしている連絡船用バースが使えないかもしれないから、時化る前にうちのボートは渡久地港に避難させることにしていた。
でもはまかぜ号が現場復帰してくれないと、ボートを渡久地港にもっていったまま島に帰ってこられなくなるので、ワタシにとっても重要だったはまかぜ号の復帰。
おかげでかろうじて雲が我慢してくれていた朝のうちに渡久地港へ行き、午後イチの便で島に戻ってくることができた。
とはいえ昼前からお昼過ぎにかけて広い範囲で激しい雷雨になって、一時はお昼の便の運航も危ぶまれたほど。
前線が直上を通過しているのだからそれなりに降るという予報は出ていたけれど、雷雨は予報上まったくノーマークだったからビックリした。
それでも風は大したことがなく、午後イチの便が出る頃には雨もほとんど上がっていて、視界不良のため欠航なんてことにならずに済んだのだった。
さてさて、一時帰沖のつもりで先週島に戻ってきてから本日で一週間、ようやくそれなりの「日常」を取り戻した気がする。
で、戻ってきてからしばらくは諸々あったけれど、ようやく落ち着いて、さぁこれから!
…というタイミングで、雨の連打(涙)。
先日も書いたように、今週末に沖縄滞在予定の旅行者のみなさんは、思いっきりハズレです、ご愁傷様。
というわけでこの日は午前中に本部町内をうろついたから、散り始めたイペーを見納めることができたものの、とにかく雨だったのでやれることといったら限られていた。
でも少しだけラッキーなことが。
先日新調のオーダーを仲宗根テントさんにしていたボートの幌と庇のテント、出来上がったら連絡すると言ってくれはしたものの、よく考えたらうちの連絡先は以前の固定電話のままになってたんじゃなかったっけか。
と思い至って、この日訪ねてみたところ、昨日できたので連絡しようと思ったら番号がわからなくて困っていた…ということだった。
そこへちょうどこの日訪ねることができたので、タイミングよく新調テントを回収することができた。
そういえば月曜日にヤンマー名護店にオーダーしていた各種フィルターが入荷したという連絡を受けたのは、一昨日名護に出かけていた際に白銀橋付近にいた頃のこと。
そのまま本部へ帰るところだったのだけど、タイミングよく連絡があったおかげでヤンマーさんまで無駄なく行くことができた。
その翌日は雨が降る前にボートで島に戻る予定だったところ、開店早々のタイミングで古堅自動車さんからピースケの車検終了の連絡が。
おかげで朝のうちにピースケを受け取りに行くことができたのだった。
いずれの場合も普段だったら島に戻ってから連絡があり、「あと1日連絡が早ければ…」ってなるものなのに、絶妙なタイミングのオンパレードってのはいったいどういうわけだ。
その昔ミスドのCMで所ジョージが歌っていたCMソング(?)を思わず口ずさんでしまいたくなるくらい、なんだかものすごくツイている感…。
話は変わる。
けっしてお安くはない受信料を税金のように強制的に徴収しておきながら、再放送番組を平気でゴールデンタイムに放送するNHKBS。
ではあるけれど、その再放送のほうがよっぽど民放地上波番組よりも面白いというこの哀しさ。
そもそも民放地上波番組などまったく観ないから、最近の番組が面白いのかつまんないのかまったく未知の世界だったものが、いろいろあってかなり長期間オタマサ実家のやっかいになっていた間に、そのありようを久しぶりに実感することとなり、結局その認識は従来といささかも変わることはなかった。
そんなNHKBS放送の数ある再放送番組のなかでも、なんで今これを?と思わずにはいられないのが、毎週月曜午後6時から放送されている「独眼竜政宗」。
朝ドラのメインキャストから大河ドラマ主役という、いわばNHKの登竜門コースどおり、「はね駒」で一躍全国区となり、翌年大河ドラマ主演となった渡辺謙が政宗役を演じていた作品だ。
それ以前の3年間近代~現代が舞台の作品が続いたあと、久しぶりの戦国時代ものということも追い風になったのだろう、「独眼竜政宗」は大河ドラマ史上空前の視聴率記録を樹立したものだった。
今改めて観てみると、画面が昔のサイズだしセットでの撮影がちゃちく見えちゃうというレトロ感はあるものの、豪華キャスト&ジェームス三木脚本はやはり見応え充分。
今ではまず望めない「歴史劇セリフをちゃんと語れる役者」のみなさんたちだらけだから(当時すでに古いファンにはセリフ回しについては文句をいわれていたのだろうけれど)、それを聞いているだけで楽しいんだけど、ふと我に返るとほとんどのヒトが故人なのだよなぁ…。
主役の渡辺謙が若武者として登場するのは10話くらいからで、それ以前は父親輝宗役の北大路欣也が物語を引っ張る。
リアルタイムで観ていた学生の頃は気づかなかったけれど、年取って落ち着いた近年と比べると、戦国武者らしく野望に燃えるその瞳のギラつき感は「仁義なき戦い・広島死闘編」で主役を演じた頃の北大路欣也のようで、その一方で主役の父親を演じる大物俳優らしい余裕もたっぷり。
現在のワタシの年齢的にも、むしろこの輝宗主役でもっと観たい!と思ってしまうほど。
10話近くまではその輝宗世代が伊達家の中心だから、帷幕に集う役者の面々も錚々たる顔ぶれだ。
やがて世代が変わって政宗が当主となると、それを支える側近たちの顔触れも変わり、西郷輝彦、三浦友和、村田雄浩になる。
若返ってこの顔ぶれ。
あ、村田雄浩って、後年の「炎立つ」で渡辺謙と初共演かと思いきや、この頃すでに共演していたのだなぁ…知らんかった。
共演といえば!
実際はどうか知らないけれど、ワタシの中ではこの「独眼竜~」が本格的ドラマ出演作だった長さんこといかりや長介が、ともすれば全員集合の時代劇コントになりそうなところを危うい線でクリアしつつ、ちゃんと主要キャストとして大事な役どころを演じているんだけど、長さんが「独眼竜~」でこの方と共演していたという記憶はなかった。

子供の頃のワタシにとっては「サントリーのおじさん」だった、神山繁。
リドリー・スコット監督の「ブラックレイン」出演がきっかけだったのか、それ以前から英語ペラペラだったから「ブラックレイン」でオファーがあったのかは知らないけれど、かつてのNHKの名物番組「英語でしゃべらナイト」に出演されたときには、流暢にイングリッシュを話していたからビックリした。
そんな神山繁と長さんは輝宗配下の重臣なのだけど、錚々たる面々の中にあってはまるでC-3POとR2-D2のような狂言回し的役回りで、2人ともまたいい味出してるんだわこれが。
ちなみにこの2人は、後年↓こういう味わい深いシーンでも共演している。

ご存知「踊る大捜査線」の副総監と和久さん。
キャリア組と現場組という立場が違えど志を同じくする2人、若い頃には警察組織を変えようと血気盛んだった彼らながら、このたび退官が決まったことを長さんに伝える副総監…というシーンだ。
このシーンがある映画2作目がワタシのなかでの長さんの遺作でもあるので、(その後神山繁も死んじゃったこともあって)セリフのひとつひとつがなんともしみじみと切ない名シーン。
でも後ろから見れば…

…単に2人のハゲおやじが座っているだけ。
特に2人に思い入れが無い若い方がご覧になれば、かなりビミョーなシーンでしかないのだろう…。
踊る大捜査線では味のある2人が、それ以前に大河ドラマで共演していただなんて、まったく覚えていなかったなぁ…。
その他、樹木希林と並び称されるほどにいつどの時代の作品でも全然変わらない大滝秀治の名演、そしてこの13年後に「葵~徳川三代~」で演じたお江役と寸分も変わらないキャラお東の方(輝宗の妻)を演じる岩下志麻の怪女ぶりもさることながら、この「独眼竜政宗」で群を抜いてとびきりスペシャルな出演者といえば、ほかでもないこの方。

ご存知勝新太郎。
政宗の前に最初に大きく立ちはだかる天下人豊臣秀吉役で出演しているんだけど、リアルタイムで観ていた10代の頃は、風貌からして勝新太郎といえば秀吉というよりも、黒澤明にクビにされた武田信玄役のほうがよっぽどあっていそう…と思ったものだった。
でもこの勝新太郎の起用なればこそ、というシーンがちゃんとあった。
とりあえず秀吉が家康を従えることとなり、天下統一まであとは北条攻めを残すのみとなった頃、血気にはやる政宗は依然秀吉の軍門に下ることを潔しとしていなかった。
そのため小田原攻めで秀吉から従軍要請があった際には致命的な遅参をしてしまい、死を覚悟しつつ秀吉のもとへ初めて参じる政宗。
死を賭しているから死に装束で、床几に腰かける秀吉の前にひれ伏していると、「面を上げい」の声がかかる。
渡辺謙が恐る恐る顔を上げていくと、そこにいるのは…
勝新太郎。
そりゃ怖いわ!
このシーンのためにこそ勝新のキャスティングだったんじゃなかろうか(再放送はまだそこまで至っていないので、あくまでもワタシの記憶だけだから間違っていたらゴメンナサイ)。
コワイといえば、よくもまぁ何カ月も登場することになる大河ドラマの主要登場人物に、勝新太郎を起用したよなぁ、NHK。
本人はかなり自由にやらせてもらっていたっぽく、観ているぶんには実に楽しそうに秀吉を演じているんだけど、勝新といえば、いつなんどきパンツから麻薬が出てくるかわかったもんじゃないヒトですぜ。
放送前に発覚するならともかく、ドラマが波に乗ってきたときにそんなことがあったら…なんてスタッフは誰も思わなかったんだろうか。
ひょっとすると、ドラマ上で秀吉が没するところまで放送された時点で吐かれたスタッフの安堵の息が、竜巻を発生させていたかもしれない…。
このドラマのキャスティングで個人的に勝新と並び称されるのが、政宗の奥さんとなる愛姫(めごひめ)の少女時代を演じるこの方。

ゴ・ク・ミ♪
彼女はそれ以前から芸能活動をしていたらしく、この前年にはNHKの番組でヒロインもしていたそうながら、ワタシをはじめとする多くの人々は、この「独眼竜政宗」で彼女の存在を初めて知ったのだった(ちなみに「男はつらいよ」の準レギュラーになるのはこの2年後から)。
1年間放送される中で彼女が出演するシーンといえば前半のほんの数話でしかないというのに、これがきっかけで世の中は美少女ブームとなり、「国民的美少女」なんて言葉もたしかこの当時からのことではなかったっけか。
彼女の成功により、二匹目のドジョウを狙った所属事務所が美少女コンテストを開催し始めたことによって、現在の大女優米倉涼子が世に出てきたそうな。
ドジョウどころかオオウナギ。
言ってみれば「独眼竜政宗」のキャスティング担当者は、「ドクターX」の生みの親でもあるのだった。
そんなゴクミも現在50歳。
そりゃ長さんもサントリーのおじさんもお星様になるわなぁ…。
1年間だけのドラマではいくらなんでも12歳がその後のオトナ役まではできないから、残念ながらゴクミは渡辺謙の登場とともに退場し、かわりにオトナ役の愛姫が登場することになる。
その愛姫のオトナ役といえばほかでもない…
桜田淳子。
そりゃあ、
~♪ようこそここへクッククック…
のほうがコントセンスはあるし、役者としても芸歴は長いし、年相応だから無難なキャスティングではあるんだろうけれど、ある意味衝撃的な変わりよう、少なくとも「ジュンコ(で)幸せ!」じゃなかったことを今でも覚えている…。
というわけで、これからいよいよ政宗時代になってきた伊達家から目が離せない今、毎週月曜午後6時から43分間はテレビの前にいるので、けっして電話をしないでくださいね。



